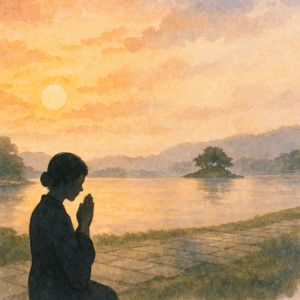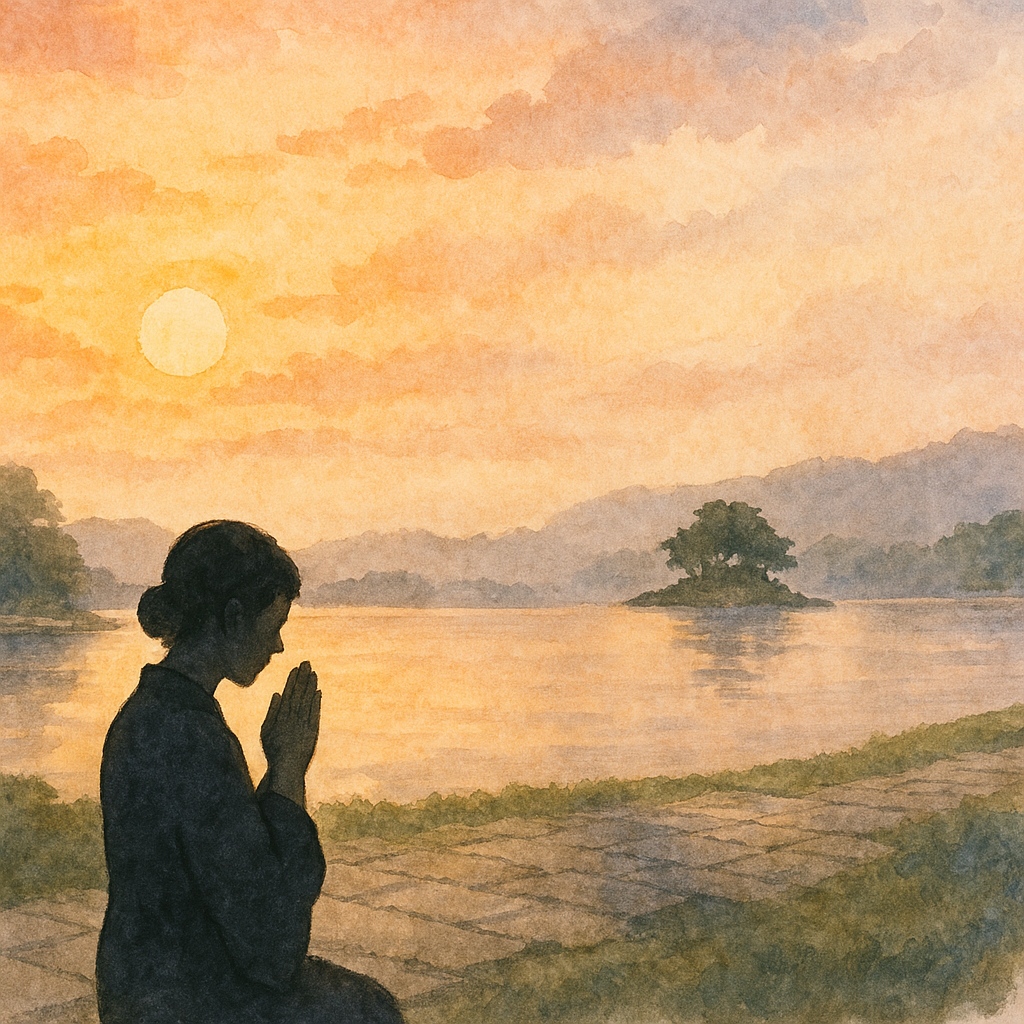
『日本の面影』(Glimpses of Unfamiliar Japan)本文
“The first of the noises of Matsue day comes to the sleeper like the throbbing of a slow, enormous pulse exactly under his ear. It is a great, soft, dull buffet of sound—like a heartbeat in its regularity, in its muffled depth, in the way it quakes up through one’s pillow so as to be felt rather than heard. It is simply the pounding of the ponderous pestle of the kometsuki, the cleaner of rice…” jrcgc.com
Lafcadio Hearn, Glimpses of Unfamiliar Japan, 1894
和訳
松江の一日を告げる最初の物音は、寝ている者の耳の真下で脈打つ、ゆっくりとした大きな鼓動のようにやって来る。規則正しく、こもった深みがあり、枕を通って震えが伝わってくるので、耳で聞くというより体で感じる、といった方がふさわしい柔らかく重い響きだ。――それはほかでもない、米を搗く**米搗き(こめつき)**の重い杵の音なのである。
NHKの朝ドラ『ばけばけ』でちょうどこの場面が流れ,その映像を観ながら、ふと胸の奥が熱くなる瞬間がありました。
松江の朝の風景、人々の営み、祈りの光景――どれも特別なことではないのに、なぜか涙が出そうになる。
それは、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が『日本の面影』で描いた日本人の“心の在り方”と重なって見えたからかもしれません。
異邦人が見た、日本の「内側の光」
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、明治の松江に暮らした異邦人。
ギリシャに生まれ、アメリカを経て日本へと渡り、この国を深く愛しました。
松江での暮らしはわずか一年ほどでしたが、彼にとって“心のふるさと”となり、
のちの著作の原点となりました。
彼が書いた『日本の面影(Glimpses of Unfamiliar Japan)』は、単なる異文化紹介ではありません。
そこには「見たことのない日本」ではなく、「感じ取った日本」が描かれています。
出雲大社や佐太神社、神魂神社、そして島根町の加賀の潜戸――
その一つひとつの風景の中に、ハーンは“日本人の魂”を見つけたのです。
それは、目に見えないけれど確かに存在する「祈り」「つながり」「自然との調和」でした。
自分の暮らしの中にある“面影”
最近になってようやく、この本を読む気持ちが生まれました。
そして読み進めるうちに、ハーンが見た「当時の日本」と、自分の暮らす「今の日本」が静かに重なっていくのを感じたのです。
自分は毎朝夕、神棚に祝詞をあげ、仏壇に手を合わせています。
特別な信心というより、生活の中の“いつもの所作”です。
でも、その姿こそが、ハーンが描いた“日本人の祈りのかたち”と同じなのだと思うようになりました。
変わることが素晴らしい時代にあって、変わらないことの中にある美しさを、最近よく感じます。
氏神様の行事に氏子の代表として参加するようになり、何百年も続く伝統の輪の中に自分がいることを実感します。
かつては「地元に残ること」が犠牲のように思えた時期もありましたが、今では「続けていけること」「受け継げること」への感謝に変わりました。
それはきっと、ハーンが見た“日本の面影”の中にも流れている、自然と共に生きるという感覚なのだと思います。
人が自然を支配するのではなく、自然と呼吸を合わせ、その中に祈りと感謝を見出す――そんな生き方が、今も自分の暮らしの根にあります。
変わることと、変わらないこと
「変わること」は、人の成長にとって大切なこと。
でも、「変わらないこと」には、人の心を支える静かな力があります。
どちらも大切で、どちらも美しい。
ハーンは『日本の面影』の中で、
“人々が何気なく守り続けている日常”に、日本人の精神を見出しました。
その精神は、今も私たちの暮らしの中で脈々と息づいています。
あなたの暮らしにある「面影」は?
ハーンが見た明治の日本も、私が生きる令和の日本も、変わりながら、同じ根を持っている気がします。
それは、朝の祈りであり、季節の移ろいであり、人と人のつながりの中に生まれる“やさしい循環”のこと。
『日本の面影』は、過去を語る本ではなく、今の暮らしを見つめ直すための“鏡”なのかもしれません。
今日のあなたの一日に、どんな「変わらない美しさ」がありますか?
今日も佳き日に
コーチミツル
(参考)『日本の面影』(Glimpses of Unfamiliar Japan)本文続き
“Then the boom of the great bell of Tokoji the Zenshu temple, shakes over the town; then come melancholy echoes of drumming from the tiny little temple of Jizo in the street Zaimokucho, near my house, signalling the Buddhist hour of morning prayer. And finally the cries of the earliest itinerant venders begin — ‘Daikoyai! kabuya-kabu!’ — the sellers of daikon and other strange vegetables. ‘Moyaya-moya!’ — the plaintive call of the women who sell little thin slips of kindling-wood for the lighting of charcoal fires.
Roused thus by these earliest sounds of the city’s wakening life, I slide open my little Japanese paper window to look out upon the morning over a soft green cloud of spring foliage rising from the river-bounded garden below. Before me, tremulously mirroring everything upon its farther side, glimmers the broad glassy mouth of the Ohashigawa, opening into the grand Shinji Lake, which spreads out broadly to the right in a dim grey frame of peaks. Just opposite to me, across the stream, the blue-pointed Japanese dwellings have their shutters all closed; they are still shut up like boxes, for it is not yet sunrise, although it is day.”
Lafcadio Hearn, Glimpses of Unfamiliar Japan, 1894
和訳
次に、町に響くのは、禅宗のお寺・東光寺の大きな鐘の一撃です。次いで、私の家の近く、材木町の小さなお地蔵様の寺から、朝のお勤めを告げる寂しげな太鼓の余響が聞こえてきます。そしてついに、朝一番の行商人たちの声が始まります――「だいこ(大根)やい! かぶやかぶ!」と、ダイコンやその他の珍しい野菜を売る声。さらに「もややーもや!」と、炭火を起こすための細い薪の切り売りをする女性たちの、切なげな呼び声。
こうして町の覚める最初の音に促されて、私は小さな和紙の窓を滑らせて開け、川に囲まれた庭から昇る、淡い春の緑の雲の上に朝を見ます。目の前には、向こう岸の景色を震えるように映しながら、幅広く鏡のように輝く大橋川の入口が見え、その川は右手へ大きく広がる宍道湖へと開いています。川を隔ててすぐ向こうには、青い屋根の和風の住居が、箱のようにすべての戸を閉ざして並んでいます。日の出前なのです、まだ明るいのに――。
#日本の面影 #ラフカディオハーン #小泉八雲 #松江の朝 #出雲神話 #神魂神社 #佐太神社 #加賀の潜戸 #祈りの時間 #変わらない美しさ #ばけばけ #NHK #朝ドラ