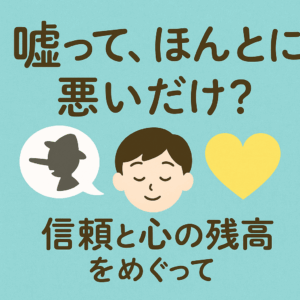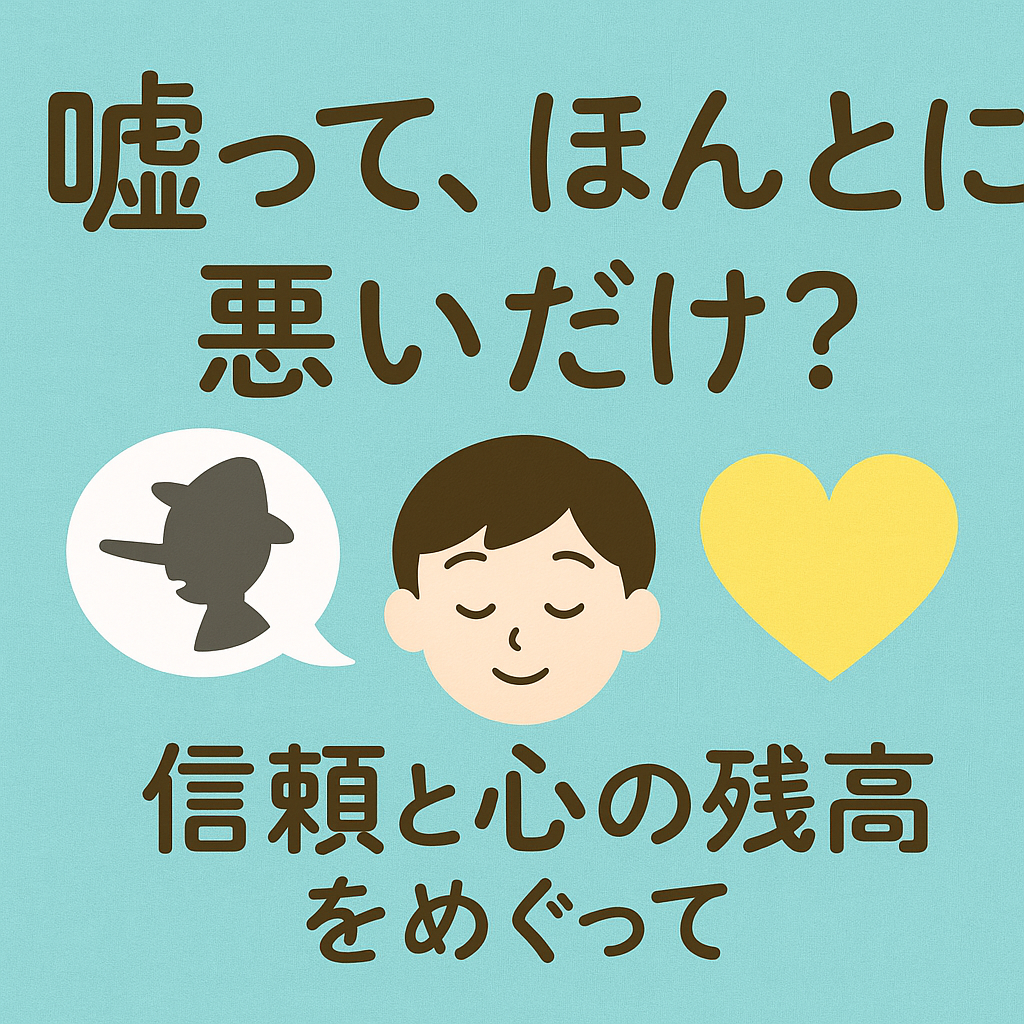
人は生きていく中で、1度とは言わず嘘をついてしまうことがあると思います。
でもその嘘が誰のためなのかによって、意味合いはずいぶん変わるように感じます。
小説『准教授・高槻彰良の推察』に出てくる深町くんは、人の嘘を見抜く力を持っています。
けれど、たとえ嘘だとわかっても、その奥にある理由までは読み取れません。
だからこそ、嘘は単純に「悪いもの」とは言い切れない…そんな時もあるように思います。
嘘にもいろいろある
- 思いやりの嘘
周りに心配をかけないよう、相手を傷つけないようにつく嘘。
たとえば体調が悪くても「大丈夫」と笑顔で答えるときなど。
ただ、カラダの不調を隠してしまうと後でかえって相手を悲しませることもあります。
一見優しく見えても、必ずしも「良い嘘」とは言えないかもしれません。 - 自分を守る嘘
体裁を保ちたい、責任を避けたい、そんな気持ちからつく嘘。
つい口をついて出てしまうこともあるかもしれません。 - 人を欺く嘘
利益のために相手をだましてしまう嘘。
これは信頼を一気に壊してしまいます。
ほんのり心が和む“良い嘘”
ここまで、お話ししてきて「良い嘘ってあるの?」と思われるかもしれません。
強いて挙げるなら、最初から“嘘だとわかる”ことで、笑いが生まれる嘘でしょうか。
- たとえば、エイプリルフールの「実は今日から空を飛べるようになった!」といった冗談。
- 子どもに向けて「冷蔵庫に妖精が住んでるんだよ」とキラキラした目で語る遊び。
みんながすぐに“冗談だ”と気づけて、ちょっと笑顔になる――
そんな軽やかな嘘なら、人と人をあたたかくつなぐエッセンスになるのかもしれません。
「信頼残高」という視点
自分は以前、ブログ「174.ためてよいもの、ためないほうがよいもの」で
「信頼残高」 という言葉を紹介しました。
これはアメリカの思想家 スティーブン・R・コヴィー が
『7つの習慣』で提唱した「感情の銀行口座(Emotional Bank Account)」の考えが元になっています。
コヴィーによると、人間関係の信頼は銀行口座のようなもの。
日々の小さな誠実さや約束を守る行為は預け入れ、
不誠実や約束破りは引き出しになり、残高が減ります。
預け入れの例
- 相手を理解しようとする
- 小さな約束を守る
- 誠実さを示す
- 期待をきちんと伝える
- 間違えたら素直に謝る
引き出しになる例
- 約束を破る
- 無礼・不誠実な態度
- 期待を放置する
見えない口座だからこそ、日々の小さな積み重ねが大切。
一度大きく引き出してしまうと、残高はあっという間に減ってしまいます。
嘘をつかれた側・嘘をついた側ができること
信頼残高が減ったと感じる場面では、立場によって選ぶ行動が変わります。
嘘をつかれた側
- 感情を認める
驚きや悲しみ、怒り…まずは自分の気持ちを無理に抑え込まない。 - 時間や距離をとる
すぐに結論を出さず、心を落ち着ける時間を確保する。 - 境界線を描く
これからどう関わるかは、自分が安心できるかを基準に決める。
嘘をついた側
- とにかく謝る
- その後のフォローとして誠意をもって行動する
- 信頼残高を増やす行動を積む(陽徳、陰徳)
嘘は一見ただの言葉のごまかしでも、人の心に影を残します。
誰かを守ろうとついた嘘が相手を悲しませることもあれば、
最初から冗談とわかる“楽しい嘘”が笑顔を生むこともあります。
そして信頼残高は、日々の小さな行動で増えたり減ったり。
嘘をついた側も、嘘をつかれた側も、誠実さを持ち続けることが
これからの信頼を守る一番の近道なのかもしれません。
あなたがこれまでについた“ちょっとした嘘”には、どんな思いがありましたか?
そして、その嘘は信頼残高を減らしましたか、それとも笑顔を増やしましたか?
今日も佳き日に
コーチミツル
#嘘 #信頼残高 #スティーブンコヴィー #准教授高槻彰良の推察 #コーチング #良い嘘