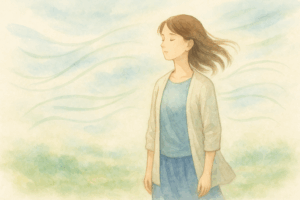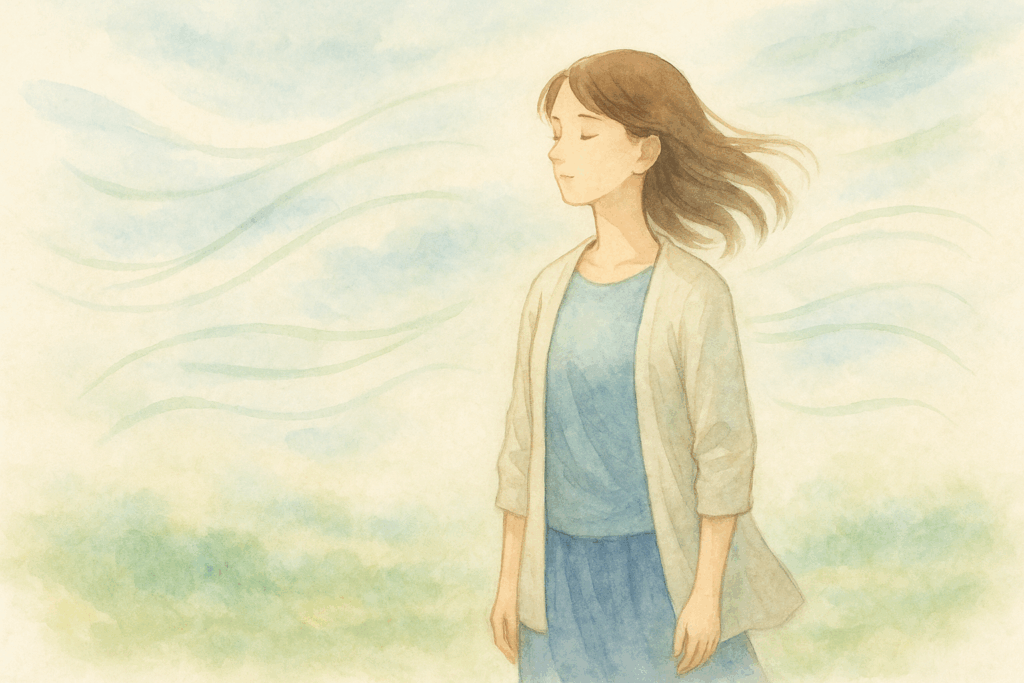
昨日のブログで、「気を遣う」「気を奪う」「気をもらう」という話をしました。
人と人との間には、“気”という見えないエネルギーが流れているように感じます。
誰かと話して元気をもらうこともあれば、逆に少し疲れてしまうこともある。
“気”は目には見えませんが、確かにそこにあり、波のように、波紋のように、私たちの間を行き来しているのだと思います。
空気を読むということ
自分は、昔から人の表情や声のトーン、その場の雰囲気を敏感に感じ取るほうです。
いわゆる「空気を読む」タイプ。
誰かが居心地よく過ごせるように気を配ったり、場の流れを壊さないように言葉を選んだりする。
それはきっと、相手を思いやる気持ちの表れであり、日本人が大切にしてきた「察する文化」でもあるのでしょう。
そして、コーチングを学んでからは、その傾向が“観察力”として磨かれてきたように感じます。
相手の小さな変化や、言葉の奥にある気持ちに気づけることが、対話を深めるうえで大切な力になっています。
空気を読みすぎてしまうとき
けれど、ときどき思うのです。
空気を読みすぎると、「自分はどう感じていたんだろう?」と後から振り返ることがある。
「ここで言うと空気が悪くなるかな」「反対したら嫌われるかもしれない」そんなふうに考えて、自分の気持ちをそっと押し込めてしまうことがあるのです。
気を遣うことは優しさ。
でも、気を使いすぎると、自分の“気”が減ってしまう。
知らないうちに心が疲れたり、少しずつ「自分」が薄れていったりします。
空気は“読む”ものではなく、“感じて選ぶ”もの
最近は、こう考えるようになりました。
空気は「読む」ものではなく、「感じて選ぶ」もの。
たとえその場の空気がどうであっても、“どうするか”の決定権は、いつも自分の中にあります。
相手の要求を汲み取って“してあげる”ことと、自分が感じて“選んで動く”ことは、まったく違う。
それは、相手のために動くようでいて、実は「自分の意思」で生きるということでもあります。
時には、あえてスルーする選択もあっていい。
すべての空気に反応する必要はないし、すべての期待に応える義務もありません。
その選択を「自分で決める」ことが、自分の気を守り、健やかに生きるための大切な境界線なのだと思います。
自分の空気を整えるということ
空気を読むよりも先に、“自分の空気”を整えること。
焦っているときは、場の空気も落ち着かなくなる。
穏やかな気持ちでいると、周りの人の表情まで柔らかくなる。
空気は外から読み取るものではなく、内側から生まれるもの。
自分の呼吸や在り方が整っているとき、そこにいるだけで、優しい空気が広がっていくのを感じます。
あなたは最近、どんな空気を感じましたか?
その空気の中で、「自分の気」はどう流れていたでしょうか。
そして、その流れを選んだのは、誰だったでしょうか。
#空気を読む #気の流れ #コーチング #観察力 #気づき #心理的安全性 #ウェルビーイング #人間関係 #CoachMitsuru #WellLog