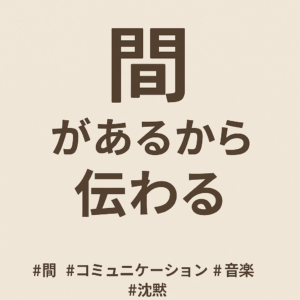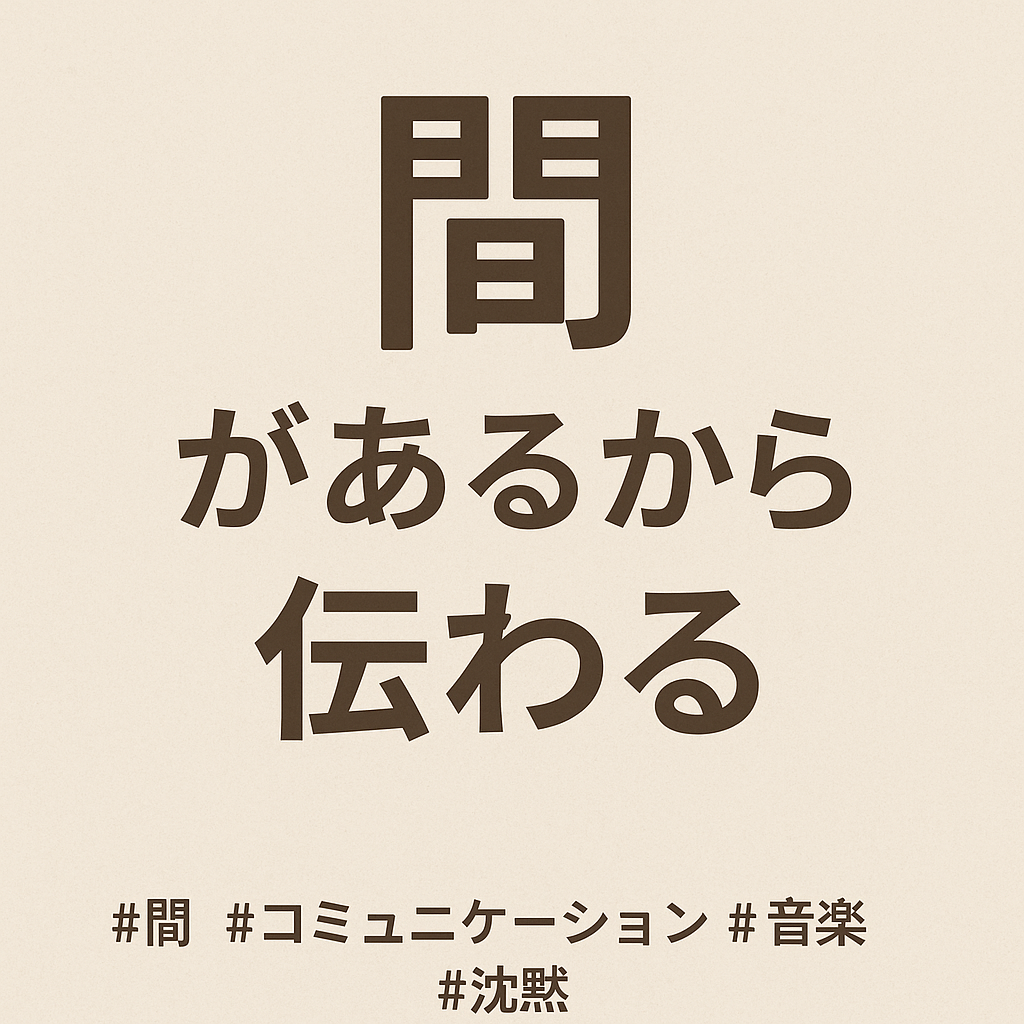
人と話すとき、音楽を奏でるとき、あるいはただ黙って誰かの隣にいるとき。
言葉や音がないその“すきま”にこそ、心が通う瞬間があるのかもしれません。
今日は、そんな「間(ま)」について、日々感じていることを綴ってみたいと思います。
「間が悪い」って何だろう?
「間(ま)」という言葉には、面白い表現がいくつもあります。
たとえば、「間が悪い」「間が抜ける」「間を持たせる」など。どれも、“タイミング”や“空気感”に深く関わっている言葉です。
日本人は昔からこの「間」をとても大切にしてきた文化があるように思います。
それは、空間の取り方、話し方、そして人と人の距離感にも表れているように思います。
コーチングでも「間」は大切
コーチングの中でも、「沈黙」を怖れずに受け止めることがとても大切にされています。
相手が考えている時間に、無理に言葉をかぶせず、信じて待つ。
そこに、信頼や安心が生まれていきます。
過去のブログ「コミュニケーションはキャッチボール」でもご紹介しましたが、言葉を投げ合うばかりではなく、ちゃんと“受け止める”という余白があってこそ、キャッチボールは続きます。
ジャズにも「間」がある
自分はトランペットを吹いていますが、ジャズセッションに参加していると、
毎回のように盛大な拍手を受ける方がいらっしゃいます。もちろん演奏が上手いというのもあるのでしょうが、
聴いていて「間」の取り方がとても自然で、美しくて、まるで一つの物語を聴いているような気持ちになります。
音を詰め込むのではなく、曲の中でブレーク(沈黙)を使って音楽にしてしまうような、そんな余裕とセンス。
自分にはまだ難しいのですが、いつかそんな「間」を感じられる演奏ができるようになりたいなと思っています。
話し方にも「間」は響く
プロ野球のヒーローインタビューなどを見ていても、
たまに拍手が自然と湧き上がるようなインタビューがありますよね。
それは、内容が素晴らしいというだけでなく、
一言ひとことの“間”が絶妙だからこそ、
聞いている側が心の中で「うん」と頷ける余裕があるのだと感じます。
自分はどうもせっかちなところがあるので、つい動作が早くなったり早口になってしまうのですが、
これからは「間を持つ」ということを、意識してみたいと思っています。
昭和のお笑いも「間」でできていた
クレージーキャッツやドリフターズの加藤茶さんや志村けんさん。
彼らはもともとミュージシャンですが、音楽で培った「間」の感覚を、お笑いの中でも見事に活かしていたのではないかと今は思っています。
次に何が来るのか?
観客が期待して一瞬静かになる——その“間”が、笑いを最大限に引き出していたのだと思います。
今見返しても、決して古く感じないのは、この「間」のセンスがあってこそなのかもしれません。
建築にも「間」の美しさがある
もうひとつ、以前書いたブログ「日本家屋の良さとは」の中でも紹介しましたが、
日本の家は「間」を大切にしてつくられています。
ただ広いわけではなく、空間の“余白”に美しさや機能が込められているのです。
それは、暮らしにも心にも、落ち着きや調和をもたらしてくれると感じます。
「間」がくれる、心の余裕
話すときも、奏でるときも、生きているときも。
「間」があるからこそ、余裕が生まれ、響きが生まれるのだと思います。
忙しない毎日だからこそ、
言葉と気持ちの間に、少しだけ“間”を持ってみる。
それだけで、何かが伝わることもあるのかもしれません。
あなたは、最近「間」を大切にした瞬間がありますか?
言葉を待つ時間、音を感じる時間、ただ隣にいる静かな時間——
どんな「間」が、心に響いたでしょうか。
今日も佳き日に
コーチミツル