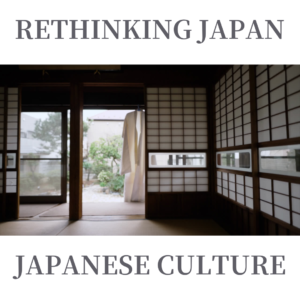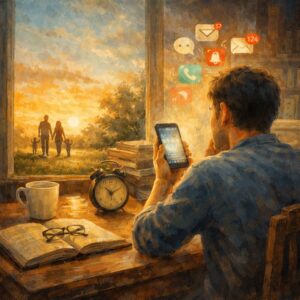今日はトイレの改修工事でした。45年ほど前に親父が家を建て替えて、その後20年前に自分がリフォームしたのですが、水洗トイレは井戸水を利用しており、水道水よりは劣化が激しいとのことでした。これまで、騙し騙しで配管などを修理していただいておりましたが、今回は水漏れが直らず、洋式の便器ごと取替となりました。
45年前に建て替える以前の実家は築200年くらいの古い家で、土間から階段のような上がり框(あがりかまち)を通じて部屋に入るような典型的な日本家屋でした。メインの部屋を玄関(の間)と呼び、その隣の奥の客間を表(の間)と言って冠婚葬祭でお客様が来られるときに使っていました。(この部屋の呼び名は自分の地方独自かもしれません)
親父が家を建て替えた時も日本家屋の伝統は残し、玄関の間と表の間の両続きの部屋を再現し、部屋の間は襖(ふすま)で分けていて、お客様の人数に合わせて襖を外したりしていました。
20年前のリフォームでは、台所やトイレ、風呂などの水回りの工事をしましたが、玄関の間や表の間の洋間化は予算がなくてそのままにしていました。その後3年前に親父が、そして今年お袋が他界し、最後は家で御棺に入りましたが、お通夜から出棺までの間、日本の伝統に習い二間の和室を使ってお客様を迎え、両親を見送ることができました。
これまで自分は、どちらかというと欧米様式のドアやフローリング、テーブルに椅子といったものにあこがれていましたが、改めて日本家屋を考えてみると、
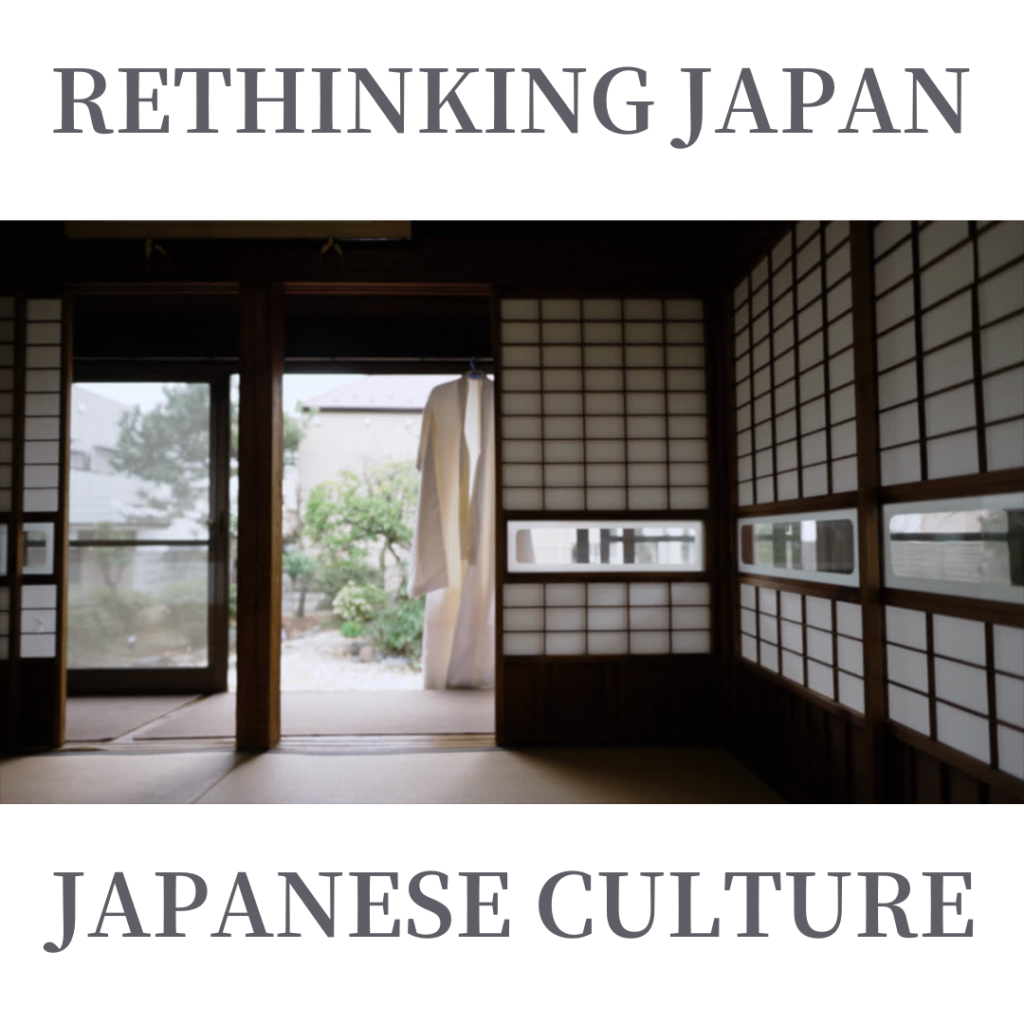
素材は?
- 木材や漆喰、珪藻土などの調湿機能が高い素材を使用している
- 畳や塗り壁、障子や襖など日本家屋を象徴する部材が使われている
間取りは?
- 縁側、床の間、書院などの独特のスペースがある
- 「玄関土間」というつくり
- 「ふすま」で部屋の間取りを変えられる
- 「引き戸」はスペースをつぶさない
その他特徴として・・・
- 日本特有の自然素材を使用している
- 伝統的な建築方法で建てられている
- 調湿機能に優れている
- 耐久性、柔軟性、耐震性に優れている
- 日当たりを重視した設計がなされている
- 風通しがよい
もう一度家を見まわし考えなおしてみると、
- 出窓はないけど明るい縁側がある
- カーテンがなくとも障子がカーテン代わりになる
- 部屋を分けるパーテーションはないけど襖で部屋の大きさを変えられる
- フローリングではないけど、カーペットを引かずとも柔らかい畳がある
- ベッドはないけど布団を敷けば寝られるし、寝ていないときは片づけて部屋を有効利用できる
- 掃除機を使わなくてもほうきで掃き出して綺麗にできる
- 椅子がなくとも座布団があればたくさんの人が座られる
などなど、機能的で素晴らしい点が沢山ありました。
ちなみに外国の方が日本の家屋に憧れる理由を調べてみると
理由は?
- 日本の伝統的な家屋への憧れ
- 昔ながらの日本らしさへの憧れ
- 日本の文化への興味
- 日本の伝統文化や食べ物、観光地への興味
- 日本の気候風土や生活習慣を土台に形作られた住宅への興味
なお、日本の住宅は、気候風土や生活習慣を土台に形作られているため、地域性や国民性からくる工夫や特徴が色濃く出ているとのことでした。
最近思うのですが、自分が子供の頃よりはるかに正座ができない人が増えているのではないかと思っています(自分は2回膝靭帯手術して、正座ができないので人のことを言えないのですが)。もちろん、椅子の生活が増えたこともあると思いますが、和風の便器のように股関節のストレッチを普段からしないことも影響しているかもしれません。足腰という意味では、日本人は退化しているようにも思います。もしかしたら、他にも生活が欧米化したことによる退化があるかもしれません。
そんなわけで、今日は日本家屋の良さを改めて感じ、併せて日本の文化や風習、歴史をしっかりと学ぶことが大切なのかなと思った次第です。
Rethinking Japan!!
今日も佳き日に
コーチミツル