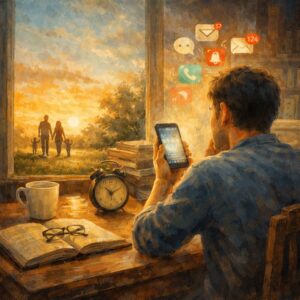春に撒いたオクラ。夏のあいだはほとんど芽が出ず、「今年はダメだったなあ」と思っていました。
ところが10月に入り、気温が下がってきた頃、なんと新しいオクラの芽が次々と顔を出し始めたのです。
さらに、初夏に掘り残していたのか、ジャガイモの葉も畑のあちこちから芽吹いていました。
肥料も農薬も使わない自然栽培に切り替えてから、思いどおりにいかないことも多かったのですが、こうして季節を越えて命が芽吹く姿を見ると、自然の力の奥深さを感じます。ただ、オクラは熱帯性の植物で、これから蝶や蜂の活動が少なくなる中、実がなるかどうかは微妙かと思っています。

ちなみに、なぜオクラが今芽吹きだしたかについてChatGPT君に訊いてみたところこのような回答がでてきました。
↓以下ChatGPT回答↓
オクラの種は硬い種皮に覆われており、乾燥や低温などの条件下では水分を吸収しにくく、発芽が遅れることがあります。特に今年のように「夏に1か月雨が降らなかった」環境では、
→ 種が土の中にあっても十分に吸水できず「休眠状態」のまま
→ 秋になって雨や朝露が増え、土壌水分が回復したことでようやく発芽したというメカニズムが考えられます。
🔹参考エビデンス
植物生理学の研究では、「種皮透水性の低い種(例:オクラ・エンバク・クローバーなど)」は乾燥後の湿潤刺激で発芽が誘導されることが知られています(Wagner et al., Seed Science Research, 2011)。
実らなくても、土は育っている・・・はず
また、初夏に撒いた大豆も、今年は1か月もの日照りに見舞われて実が小さく、農薬を使わないために虫にも食べられてしまいました。

それでも、大豆の根には「根粒菌(こんりゅうきん)」という小さな菌が共生しています。
根粒菌は大気中の窒素を取り込んで、植物が使える形に変える働きをしてくれるため、土地そのものを豊かにしてくれる存在です。
たとえ目に見える成果が少なくても、土の中では確かに良い循環が生まれている。
自然栽培を始めてから、そんな“見えない成長”に目を向けるようになりました。
見えるか、見えないかは「知っているかどうか」
ふと感じたのは、もし自分がオクラやジャガイモの葉の形を知らなかったら、草刈り機でまとめて刈ってしまっていたかもしれないということです。
知っているからこそ、「あ、これは大切なものだ」と気づける。
それは畑だけでなく、人生にも通じるように思います。
たとえば、地面に転がっている石の中に、もし瑪瑙(めのう)や翡翠(ひすい)が混じっていても、その価値を知らなければただの石です。
「知る」ということは、世界の中にある“価値”を見分ける力を与えてくれるものだと実感します。
何のために勉強するのか?
多くの人が「勉強する意味って何だろう?」と感じたことがあるかもしれません。
試験のためでも、資格のためでもなく、本来の学びとは「見える世界を広げるため」にあるのだと思います。
心理学者デイヴィッド・オズベル(David Ausubel)は、人が新しい知識を得るとき、それは“すでに持っている知識とのつながり”によって意味づけられると述べています。
つまり、知識は単に情報の積み重ねではなく、「世界をどう見るか」を形づくるものなのです。
また、教育学の研究でも、知識を持つことで観察力が高まり、他者や自然現象をより正確に理解できることが報告されています(Bransford, Brown, & Cocking, How People Learn, 2000)。
自然から学ぶ、学びの本質
畑に出るたびに、植物たちは教えてくれます。
「学ぶ」というのは、本や机の上だけで完結するものではなく、日々の出来事や自然の変化の中にこそ本質があるということ。
オクラの芽が遅れて出てきたように、「学びのタイミング」も人それぞれです。
今は実らなくても、いつか芽を出す日がくる。
そのときに備えて、心と知識の土を耕しておくことが、勉強する意味なのかもしれません。
あなたにとって、「知ることによって見えるようになった世界」は何ですか?
そして今、どんな芽があなたの中で静かに育ちつつあるでしょうか。
今日も佳き日に
コーチミツル
#自然栽培 #大豆 #根粒菌 #学びの本質 #知識の力 #観察力 #オクラの芽 #ジャガイモ #勉強の意味 #畑からの気づき #ウェルビーイング #コーチミツルブログ