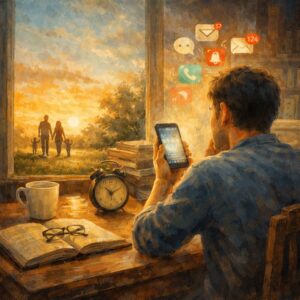先日、YouTubeですでにお亡くなりになっていますが有名な政治家である田中角栄氏のスピーチを聴いていました。
力強く、深みのある言葉に惹き込まれ、
「これは貴重な録音だな」と思いながら耳を傾けていたのです。
ところが途中で、「家族(かぞく)」という言葉を「いえぞく」と読んでいるのに気づき、
一瞬、あれ?と思いました。
――そんな読み方をするだろうか。
調べてみると、それはAIによって生成された音声だったそうです。
本人の声にそっくりでも、
どこか“人が語る言葉”とは違う。
その瞬間、ゾワッとするような不思議な感覚がありました。
AI音声は、もう「誰でも作れる」
かつては専門家しか扱えなかった音声合成も、
今ではクラウドサービスを使えば数分で生成できるようです。
たとえば、
- ElevenLabs
- CoeFont
- Voicevox
- OpenAI TTS
といったサービスがあり、テキストを入力するだけで自然な日本語のナレーションを作れるそうです。
さらに、数十秒の音声データを学習させれば、
その人の声質を再現する「ボイスクローン」 も可能といわれています。
つまり、技術的には特別な知識がなくても本人のような声を作れてしまう時代なのです。
だからこそ問われる「倫理」と「敬意」
誰でも作れるということは、誰でも悪意なく越えてしまうラインがある、ということでもあります。
たとえば、
- 故人の声を模倣して語らせる
- 本人が言っていない内容を“名言”として広める
- 許可なく声を利用する
こうした行為は、著作権や肖像権だけでなく、
人としての敬意(リスペクト) にも関わる問題だといわれています。
便利さの裏には、
「誰かの人生」や「言葉の重み」を軽んじてしまう危うさが潜んでいる――
そのことを意識しておくのが、AI時代の新しいマナーなのかもしれません。
技術を使うかどうかは「意図」で決まる
AI音声を使うこと自体は悪いことではありません。
ナレーションの補助や、視覚障がい者支援など、
人の可能性を広げる素晴らしい使い方もあるそうです。
ただ、使うときに問われるのは、“なぜその声を使うのか”という意図です。
- 誰かの声を真似て注目を集めたいのか
- 伝えたいメッセージをより伝わりやすくしたいのか
- それとも、感謝や敬意を表したいのか
同じ技術でも、意図が違えば結果はまったく違うものになると感じます。

コーチとして感じること
AIがどれだけ本物の声を再現しても、
心や精神までは再現できません。
たとえば、著名人の講演会を生で聴き、
その熱や間、息づかいに感動して涙が出ることがあります。
あの瞬間に伝わっているのは「言葉」ではなく、
**言葉を超えた“エネルギー”や“存在感”**です。
以前もブログで触れましたが、メラビアンの法則によると、
人が相手から受け取る印象のうち、
- 言葉は7%、
- 声のトーンが38%、
- 表情や仕草が55%
を占めるといわれています。
つまり、言葉以上に大切なのは、
声の響きや身体の表現、そして精神の状態なのだと思います。
AIはその“声”を真似ることはできても、
その人の「生き方」や「魂の震え」までは再現できません。
だからこそ私はこう感じます。
「AIで作れる声」よりも、
「人が心を込めて語る声」にこそ、
人の心を動かす力が宿っている。
あなたが心を動かされた“声”――
それはどんな場面で、どんな想いが込められていましたか?
今日も佳き日に
コーチミツル
#AI音声 #ボイスクローン #コンプライアンス #倫理と敬意 #メラビアンの法則 #声の力 #コーチミツル #WellLog #心を整える