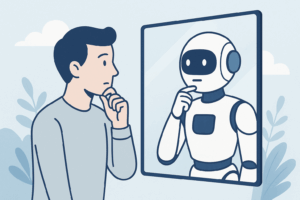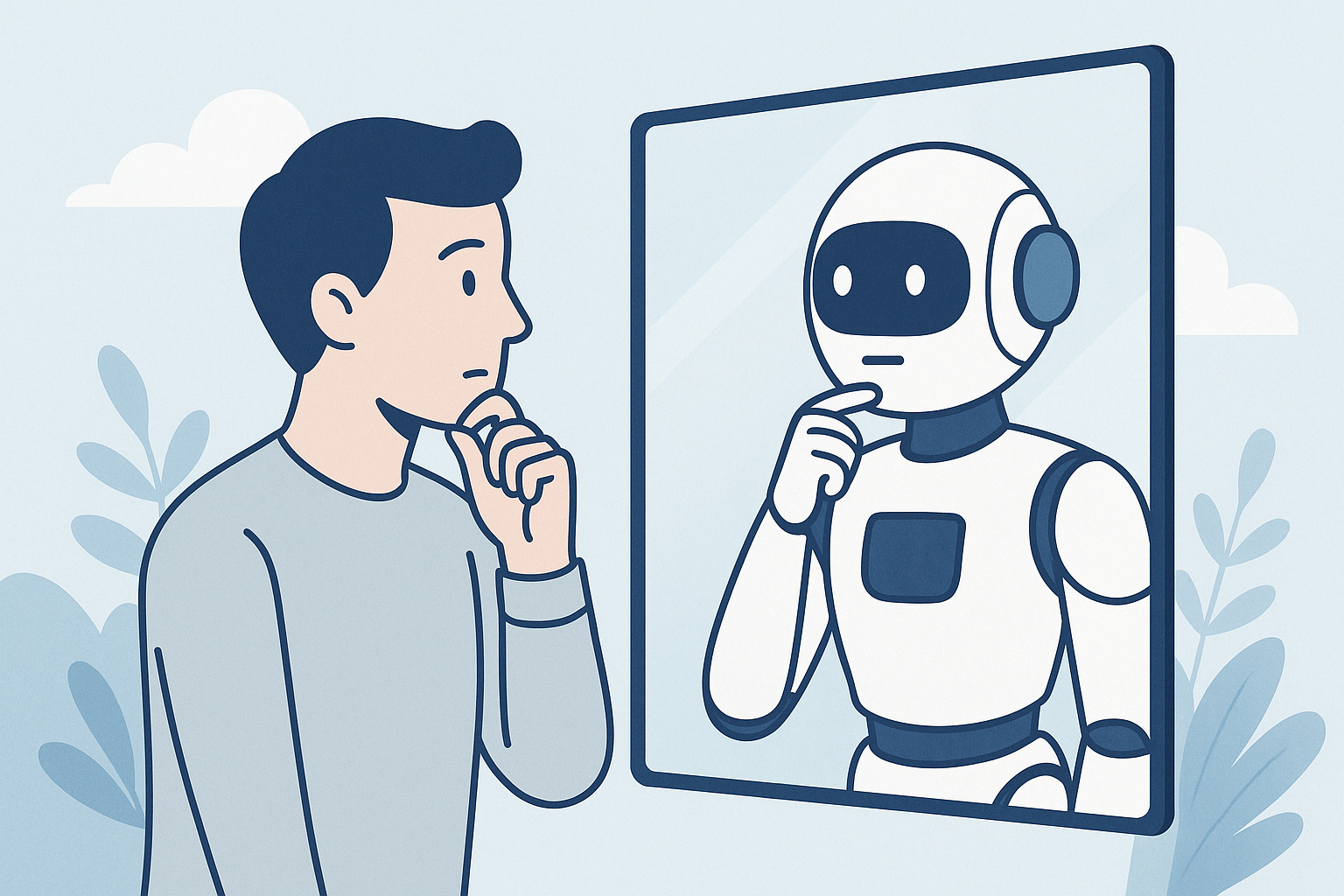
最近、AIの話題をよく耳にします。
先日、こんな記事を読みました。
👉 AIが事実と異なる情報を語ることのリスク(SmartNewsリンク)
この記事を読んで、あらためて思いました。
AIの答えをそのまま信じてしまうのは、やはり少し危うい。
でも、それはAIだけの問題ではなく、人間の思い込みにも似たところがあるように感じます。
ハルシネーション(Hallucination)とは
「ハルシネーション(hallucination)」という言葉は、
もともと心理学や医学の分野で使われ、
実際には存在しないものを“あるように感じる”現象を指します。
AIの世界でもこの言葉が使われていて、
根拠のない情報を“それらしく”語ってしまうことを意味します。
AIは人のように理解して話しているわけではなく、
「もっとも自然に見える言葉の並び」を予測して出しているだけ。
そのため、情報が足りないときは「ありそうな話」を作り出してしまうのです。
それでもAIを信じてしまう理由
AIの答えは流暢で、自信がありそうに見えます。
だからこそ、「本当に正しいのかな?」と立ち止まるのが難しい。
自分もAIを使っていて、「なるほど」とうなずくことがありますが、
後で確かめると、少し違っていた…という経験もあります。
この「もっともらしさ」こそが、AIのハルシネーションをやっかいにしています。
エビデンス(Evidence)を確かめる習慣を
AIに「根拠(evidence)を示して」とお願いすると、
信頼できる情報(論文・報道・公式データなど)を探そうとします。
これは、誤りを減らすうえでとても良い方法です。
ただ、それでも完全に正しいとは限りません。
AIが引用した情報が古かったり、少し違っていたりすることもあります。
だからこそ、最後に確かめるのは自分自身なのだと思います。
人にもある「思い込みのハルシネーション」
AIだけでなく、人の心にも同じようなことが起こります。
たとえば、
- 「あの人は自分を嫌っているに違いない」
- 「みんなが言っていたから本当だろう」
- 「一度失敗したら終わりだ」
これらも、確かめてみるとそうではないことが多いものです。
つまり、心の中で作り出した“幻”を現実と思い込んでしまう。
AIも人も、形は違っても「思い込み」という共通点を持っているのです。
幻に惑わされないための3つの視点
- 「それはどこで知ったの?」
情報源をやわらかく確かめてみる。 - 「他の見方もあるかもしれない」
一つの考えに偏らず、別の角度から見てみる。 - 「自分の気持ちはどこに傾いている?」
信じたい気持ちが判断を曇らせていないか観察する。
これらは、AIだけでなく、人との関わりにも大切な習慣です。
結びに
AIが進化しても、人の「確かめる力」はなくてはならないと思います。
「本当にそうだろうか?」と一呼吸おくこと。
その小さな慎重さが、幻から自分を遠ざけてくれるのではないでしょうか。
そして次回は、この「確かめる力」をさらに深める方法として、
“反論”という名の確認の力について考えてみたいと思います。
今日も佳き日に
コーチミツル
#AIハルシネーション #hallucination #思い込み #エビデンス #確認の習慣 #心の幻 #コーチング思考 #慎重さ #自己観察 #WellLog