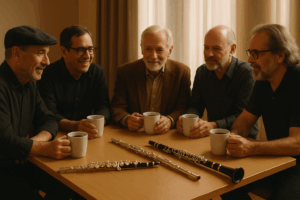コンボ練習のコーヒー休憩で出た「長生きの話」
今日は月に一度のコンボ練習でした。
リズム隊のみなさん、トロンボーンさん、自分を含めた編成で、心地よく音が重なり合う時間。
途中の休憩では、椅子に座って紙コップのコーヒーを飲みながら、ゆったりとした雰囲気で話が始まりました。
その中で、ドラムのメンバーの方がふとこんなことを言われました。
「音楽してる人って、なんだか元気だよね。認知症にもなりにくい気がするよ」
その言葉から話題が広がり、プロのジャズクラリネット奏者 北村英治さん の名前が出てきました。
北村さんは 1929年生まれ・現在96歳(2025年)。
70年以上のキャリアを持ちながら、今も現役で演奏を続けておられます。
その姿を思うと、「音楽ってやっぱり身体と心に良いんだよね」という話に、自然と説得力が生まれていました。
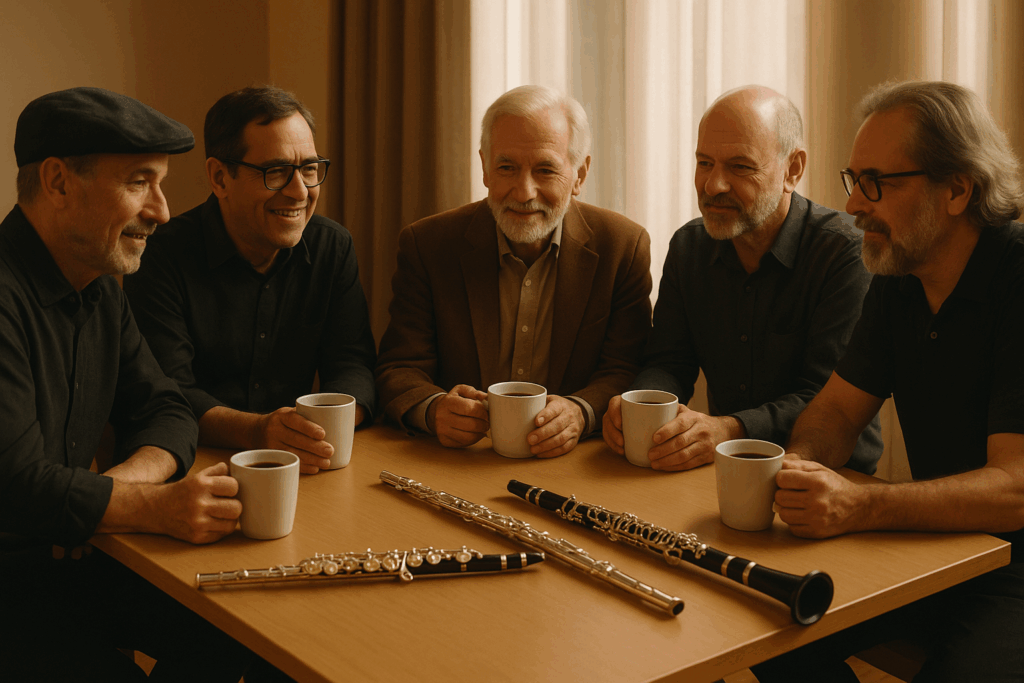
フルートの倍音、そして“身体に届く音”
休憩中にさらに話が続き、ベースさんがこう言われました。
「フルートって倍音が多いらしくて、身体に効くらしいよ。聴こえない振動が体に伝わるってテレビでやってたよ」
たしかにフルートは、空気そのものを震わせるような柔らかい音で、倍音が豊かに含まれています。
そして自分自身も、演奏中に 音が身体に届く瞬間 をよく感じます。
特に ベース・ドラム・ピアノのリズム隊の重低音や、弦の響き。
胸の奥で“ズワン”と鳴るような瞬間や、身体がスッと軽くなるような振動があります。
音を「耳で聴く」だけでなく、「身体で感じている」という感覚。
今日の会話は、そのことを改めて思い出すきっかけになりました。
■ 以前、自分のブログで書いた「音楽の効果」は“振動以外の視点”だった
そういえば、自分も過去のブログ(No.2365)で、音楽が身体や心にどんな効果をもたらすか をまとめていました。
その時は“振動”よりも、音楽が脳や心に与える作用 を中心に書いていました。
主にこんな内容です:
- 楽器演奏は「読譜・判断・集中・呼吸・運動」を同時に行う
- そのため脳の前頭前野が刺激され、思考力・判断力の向上につながる
- 音楽のリズムは自律神経を整え、気持ちの安定に寄与する
- ジャズ特有の“瞬時の判断”が、脳にとても良い刺激になる
今回の休憩の会話で、そこに 倍音や振動という“身体からの視点” が加わり、音楽の効果がより立体的に感じられるようになりました。
音楽は、脳と心と身体の全部に働きかけてくれる。
そんな気づきを受け取った時間でした。
ラッパを再開して感じている「頭のキレ」
自分もラッパを再開してから、
- 頭の切り替えが速くなった
- 集中の“入り”が早い
- 一日が軽やかに動ける
という実感があります。(あ、人はどう思っているかわかりませんが…(笑))
年齢を重ねながらも、“演奏を続けていること”が自分の身体と心を養ってくれているように感じています。
音楽の力って、やっぱり大きいですね。
最後に問いかけを
何かの演奏を聴いている時に、体で感じた瞬間がありますか?
その“響き”は、あなたのどこに届きましたか?
今日も佳き日に
コーチミツル
#音楽の力 #ジャズのある暮らし #倍音 #フルート #認知症予防 #コンボ練習 #96歳の現役 #リズム隊の響き #ラッパ再開 #音の振動