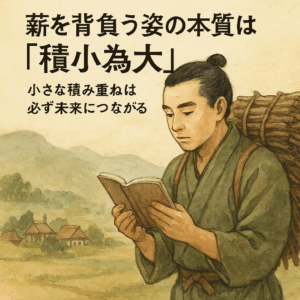「歩きながら読書」の象徴が伝えていること
前回まで、金次郎像や尊徳の“仕組みをつくる人”としての側面を見てきました。
今回は、尊徳の思想の中心である 「積小為大」 に焦点をあてます。
歩きながら読書したかどうかよりも大切なのは、「学びたいなら、時間と環境を自分でつくる」
という姿勢でした。
夜に勉強するための行灯の油が買えず、菜種を育て、収穫し、油にして灯りをともしたという話も、その象徴です。
大事なのは、“与えられるのを待つのではなく、工夫して前に進む姿勢”。その心が積小為大につながっています。
積小為大 ― 小さな行動がやがて大きな力になる
尊徳の言葉に、
「小を積んで大をなす」
というものがあります。
これは単なる努力論ではありません。
むしろ、成果への正しいプロセス を示したものです。
- いきなり大きなことはできない
- 小さな行動を毎日積み重ねる
- 気がつくと大きな実りにつながっている
尊徳が村の再建に成功したのも、村人に“大きな変化”を求めなかったからです。
まずは、小さな成功体験を積み上げることに集中しました。
積小為大は“習慣づくり”の考え方と一致している
尊徳の改革は、村の行動習慣を少しずつ変えるプロジェクトでした。
いきなり村の全体像を変えるのではなく、目の前の行動を整え、それを続けることで、村全体の文化を変えたのです。
これは、現代の生活でも、チームでも同じです。
朝自活という“小さな積み重ね”
自分が続けている朝自活も、「自分にできる“積小為大”」だと感じています。
- その日の学びを入れる
- 身体を整える
- 思考を整理する
- ブログを書く
- 心の時間を確保する
どれも、小さなことの積み重ねです。
でも、その積み重ねは無駄になりません。(そう信じたいです(笑))
気づけば、身についた知識、整った習慣、落ち着いた心が、毎日の土台になっていきます。
尊徳のレベルにはとても及びませんが、自分にできる小さな積み重ねを大事にするという点では、同じ方向を向いているのだと思います。
チームも“小さな積み重ね”で文化が育つ
チームビルディングでも、積小為大の考え方は大きな力を持ちます。
- 一言の声かけ
- 小さな振り返り
- 成果の共有
- 感謝を伝える
- 無理のない行動を揃える
こうした1つ1つはとても小さいけれど、続けていくとチームの空気が変わり、「このチームらしさ」が育っていきます。
小さく積むことは、必ず未来につながります。
最後の問い
あなたが明日から積み重ねたい“ひとつの行動”は何ですか?
そして、それが続いていくと、どんな未来が見えてきそうですか?
次回予告(第4回/全4回)
最終回では、尊徳が徹底した
「関係性を壊さない改革」
という普遍の価値について見ていきます。
“真理は変わらない”とはどういうことなのか。
このシリーズの締めとして一緒に探っていきます。
今日も佳き日に
コーチミツル
二宮尊徳 #積小為大 #小さな積み重ね #行動の習慣化 #報徳思想 #学び続ける姿勢 #村の再建 #朝自活 #WellLog #チームビルディング