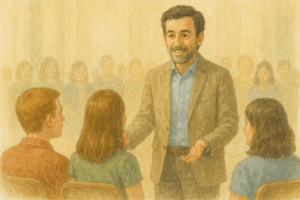研修会や講演などでファシリテーションをしているとき、
自分はなるべく聴いてくださる方の顔や目を見るようにしています。
とはいえ近視なので、はっきり見えているわけではありません。
表情や雰囲気を感じ取るようにしているだけです。
ところが、相手がまっすぐ自分の方を見つめてくださると、
少し恥ずかしくなって別の方へ視線を移してしまうことがあります。
――きっと、同じような経験をされた方も多いのではないでしょうか。
アイコンタクトの本当の目的
アイコンタクトは、単に「見る」ことが目的ではありません。
それは、「相手を尊重している」という気持ちを伝えるための手段です。
心理学者アルバート・メラビアンの研究(1971)では、
コミュニケーションにおいて言葉よりも**非言語的要素(表情・視線・声のトーンなど)が93%**の影響力を持つとされています。
つまり、どんな言葉を使うかよりも、
「どんなまなざしで相手に向き合っているか」が大切なのです。
見つめすぎは逆効果
社会心理学の研究(Argyle & Dean, 1965)によると、
会話におけるアイコンタクトの最適な割合は30〜60%。
見つめすぎても、視線を外しすぎても、相手に負担を与えてしまうことがあるといわれています。
ファシリテーションの場では「見る」ことよりも「流れるように視線を回す」ことが大切です。
参加者一人ひとりに2〜3秒ずつ視線を向け、
“会場全体を包み込むように見る”ことで、安心感が広がります。
恥ずかしがり屋におすすめの「ソフトフォーカス法」
近視で、じっと見つめるのが苦手な自分のような人には、
「ソフトフォーカス法」がおすすめです。
相手の目そのものではなく、眉・鼻・頬の三角ゾーンをやわらかく見るようにします。
相手からは「目を見て話している」と感じられつつ、
自分の心理的負担はぐっと減ります。
話す内容の節目ごとに視線を移動させると自然になります。
- 問いかけるとき → 相手の目のあたりを見る
- 説明するとき → スライドや資料に目を向ける
- まとめるとき → 会場全体を見渡す
これが“視線の呼吸”です。
質問や意見を聴くときのアイコンタクト
質問を受けたり、参加者の感想や意見を聴くとき、
相手と目を合わせることはとても大切です。
人は話している間、相手が自分に注意を向けてくれていると感じると、
話の内容を整理しながら安心して話すことができます。
聴く側が軽くうなずきながら相手を見ていると、
「受け止めてもらえている」「ちゃんと聴いてもらえている」という安心感が生まれます。
これはコーチングでも同じで、
アイコンタクトは“評価ではなく共感”のサインです。
相手を観察するようにではなく、**「あなたの言葉を大切に聴いています」**という姿勢で視線を交わすことが信頼を深めます。
あえてアイコンタクトをしないほうが良い場面
一方で、すべての場面で視線を合わせることが正解とは限りません。
たとえば、自分の中にどうしても相手を受け入れきれない気持ちがあるとき。
たとえば、相手がまったく違う思想を持っていて、
自分がその価値観を咀嚼する余裕がないときなどです。
そのようなときに無理に視線を合わせると、
表情にわずかな抵抗感が出てしまい、かえって相手に緊張を与えてしまいます。
そんなときは、**「聴き流す勇気」**を持つのもひとつの選択です。
相手の言葉を遮らずに受け止めるけれど、無理に共感しようとはしない。
その“距離の取り方”もまた、健全なコミュニケーションの形です。
また、相手が自分の話にまったく関心を持っていないときも、
過剰なアイコンタクトは意味を持たないことがあります。
ただし、相手の表情に少しでも理解や納得の兆しを感じたなら、
その瞬間にしっかり目を合わせる。
――その「タイミングの一瞬」が、信頼関係の種になります。
目的別・視線の使い方
| 目的 | 視線の使い方 | 効果 |
|---|---|---|
| 理解を促す | 相手の顔を見る | 反応を見ながら調整できる |
| 安心感を与える | 全体を包むように見る | 優しい雰囲気が伝わる |
| 自信を示す | 一人に2〜3秒しっかり合わせる | メッセージに説得力が出る |
| 共感を引き出す | 軽く目を合わせてうなずく | 心理的距離が近づく |
| 受け入れられない時 | あえて聴き流す | 無理をせず誠実さを保てる |
| 関心が薄い相手に | 一瞬のタイミングで合わせる | 興味のきっかけをつくる |
過去記事とのつながり ― “まなざし”は「場をつくる力」
このテーマは、以前のブログ
🔗 「講師にとってのプレゼンスとは? (アイコンタクトの力と「分かりやすさ」の工夫)」
でも触れた内容と深く関係しています。
その中で、自分は「プレゼンス(存在感)」を支える10の要素の一つとしてアイコンタクトを紹介しました。
にらむようではなく、安心感を与えるまなざしを意識する。
それが、聴き手の理解と集中を自然に引き出す――と書きました。
また、もうひとつの関連テーマとして、
🔗 「阿吽(あうん)」
の記事があります。
ここでは、言葉を超えて“呼吸が合う”感覚を「阿吽の呼吸」として紹介しました。
まさにアイコンタクトとは、言葉を交わさなくても気持ちが通じ合う瞬間――
**“まなざしによる阿吽”**なのだと思います。
「見る勇気」より「聴くまなざし」を
アイコンタクトは「相手を見る」ことではなく、
「相手を聴く」ためのまなざしだと感じます。
恥ずかしがり屋であっても、
相手を理解しようとするその意志が伝われば、
それだけで十分に信頼は築けます。
自分もこれからは、“見る勇気”よりも“聴くまなざし”を大切にしていきたいと思います。
あなたは、人と向き合うとき、どんなまなざしを意識していますか?
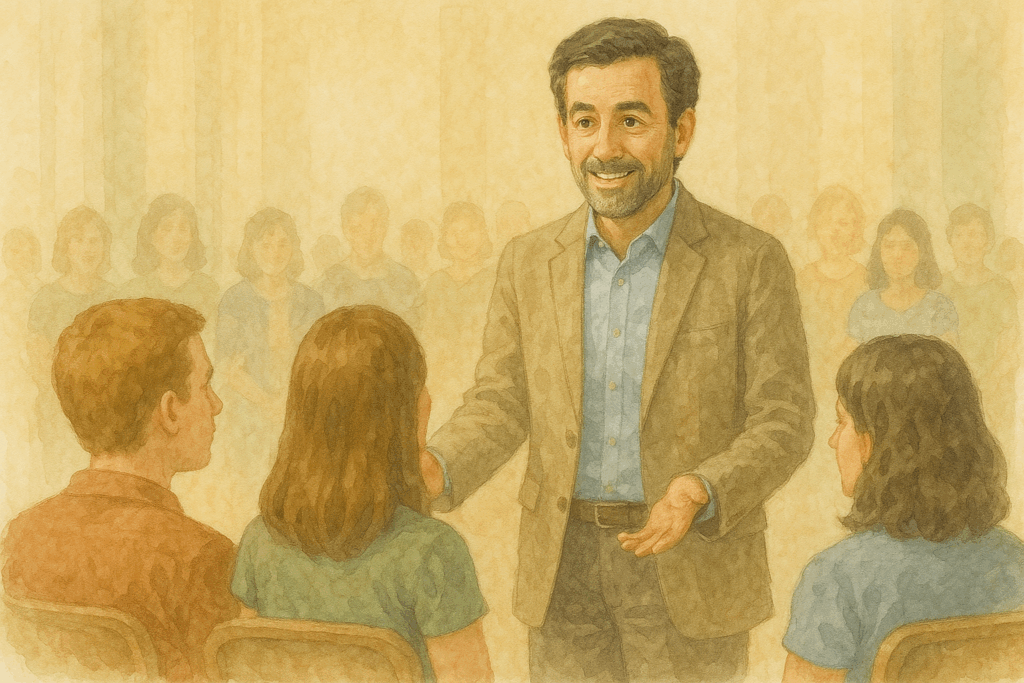
#アイコンタクト #ファシリテーション #非言語コミュニケーション #プレゼンス #阿吽の呼吸 #コーチング #聴く力 #話す力 #心理的安全性 #受け入れる力