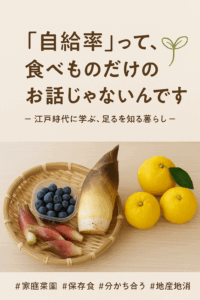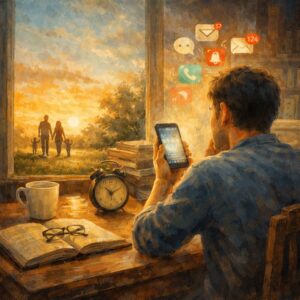最近、家庭菜園で野菜を育てたり、梅干しを漬けたりしています。
小さなことですが、手をかけて育てたものが食卓にのると、どこか誇らしく、季節のうつろいも感じられます。
そんな暮らしを楽しむ中で、「自給ってなんだろう?」と気になり、ChatGPTに調べてもらいました。
今の日本の自給率(ChatGPT調べ)
- 食料の自給率(カロリーベース):約38%(2023年)
お米はほぼ100%国産、小麦や大豆は10%未満 - エネルギー自給率:約15%
- 薬の原材料:およそ70〜80%が輸入
- 肥料や衣類の素材:ほぼ輸入頼み
私たちの暮らしは、実は世界中からの支えで成り立っていることを改めて感じました。
自給率が低いと何が起こる?
輸入が止まったり、価格が上がったりすると、
食べものや薬、エネルギーが手に入りづらくなる可能性があります。
だからこそ、自分でまかなえる力が少しでもあると、安心につながります。
江戸時代は“あるもので暮らす”時代
輸入に頼れなかった江戸時代は、
地元の食べものや自然の力をうまく活かして暮らしていました。
保存食や手仕事が当たり前で、
ものを大切にし、工夫して、分かち合う文化が根づいていたようです。
自給がつなぐ、人とのご縁
最近、裏庭で採れた茗荷をお裾分けしたら、ブルーベリーをいただいたり、
掘ったたけのこを配ったら、「良かったらどうぞ」とサザエをもらったり。
ローズマリーや柚子を軒先に置いていたら、「ありがとう」と声をかけてもらったこともあります。
自分で育てたものが、思いがけず人とのつながりを生んでくれる。
それは、自給のもうひとつの喜びなのかもしれません。
暮らしの中の「ちいさな自給」
全部自分で、は難しくても、ちょっとしたことならできるかもしれません。
- ベランダでハーブを育てる
- 味噌や梅干しを仕込んでみる
- 生ごみをコンポストで土に返す
- 手回しラジオやソーラーライトを備える
自分で支えるちからは、
どこか心を落ち着かせてくれます。
「自給率」という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれません。
でも、実は暮らしの中にある、ちいさな手間や工夫の積み重ね。
そしてそれは、自分を満たし、誰かとつながるきっかけにもなってくれるものだと感じています。
あなたは、どんな“ちいさな自給”を始めてみたいですか?
そして、それを誰と分かち合いたいですか?

今日も佳き日に
コーチミツル
自給暮らし #家庭菜園 #保存食づくり #分かち合いの暮らし #地産地消 #梅干しづくり #江戸時代の知恵 #ローカルライフ #ご近所つながり #ちいさな自立