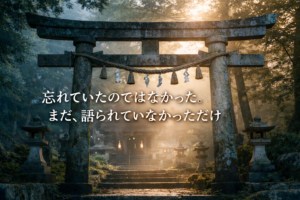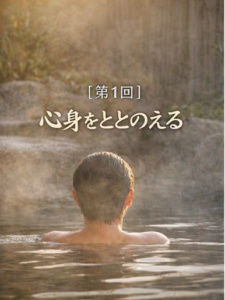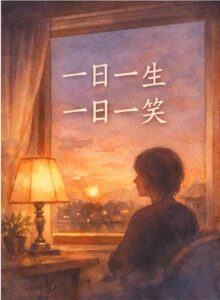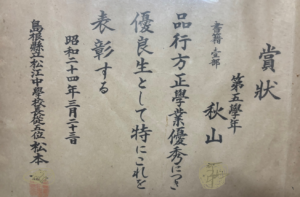最近、AIの進化には本当に目を見張るものがあります。
ChatGPTのように、質問すればすぐに答えてくれて、言葉のやり取りもスムーズ。
ときには「自分より頭が良いのでは」と思うこともあるくらいです。
そんな中、ある研究者の言葉に、深く心を動かされました。
東京大学准教授の鈴木俊貴さん。
鳥の「言葉」を研究する動物言語学者として知られる方です。

鳥の言葉を解明した研究者の姿勢に、共感
鈴木准教授は、シジュウカラという鳥が「文法のある言葉」を使って仲間と意思疎通していることを明らかにした方です。
その発見の裏にあったのは、最先端の機械ではなく、
ひたすら自然の中で、じっくりと観察を重ねる姿勢でした。
「とにかく観察です。びっくりするくらい、ずっと観察ばかりしてきました」
この言葉を読んだとき、自分の中にあったぼんやりとした感覚が、ことばになった気がしました。
AIと人との違いは、今のタイミングでの「観察力」かもしれない
ChatGPTのようなAIは、これまでに蓄積された情報を高速で処理し、答えを導き出してくれます。
けれど、目の前にある現実を「観察する力」は持っていません。
たとえば、人の表情の微妙な変化、言葉にしない沈黙、風のにおいや空気の湿り気…。
それらに気づくのは、人の感覚だからこそできること。
鈴木准教授の研究も、こうした**「目に見えにくい違い」を丁寧に見つめる力**があったからこそ、鳥の言葉という繊細な現象を捉えられたのだと感じました。
観察力は、自然との対話から育つ
鈴木さんが観察していたのは、森に住む鳥たちでした。
自分が日々向き合っているのは、庭の木々や畑の草花です。
環境は違っても、「観る」という行為に込められた想いには、どこか通じるものがあります。
たとえば、昨日と今日の葉っぱの色の違い。
咲いたばかりの花の向き。
畑の土の湿り気や、野菜の葉の表情…。
こうした自然の“語りかけ”のような変化に気づくたび、
「人は観察を通じて、世界と対話しているのだな」と感じることがあります。
コーチングの現場でも、観察がすべて
鈴木さんは動物の観察を通じて「言葉の意味」に気づきましたが、
人のコーチングの現場でも、やはり大切なのは観る力です。
相手の言葉に耳を傾けるだけでなく、
その時の声のトーンや沈黙、手の動きや視線のゆらぎ…。
言葉に現れない部分を丁寧に観察することで、
「この人は今、何を大切にしようとしているのだろう」
そんなことが、ふっと浮かんできます。
AIのように即答はできなくても、
時間をかけて、じっくりと観ることから生まれる“気づき”がある。
そんなふうに、鈴木さんの研究とコーチングの共通点を感じています。
鈴木准教授の姿勢に学ぶ、観察力の磨き方
では、自分たちも日々の暮らしの中で、観察力を育てていくにはどうすれば良いのでしょうか。
鈴木さんの研究姿勢に共感しながら、実践できそうな方法をまとめてみました。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 自然の中で“ただ見る”時間をつくる | 鳥のようすや雲の動きを、目的もなく眺めてみる |
| 「違い」を探す遊びをしてみる | 昨日との変化、左右の違いなど、微差を楽しむ |
| 沈黙の時間を味わう | 会話の“間”に注意して、表情や空気の変化に気づく |
| 五感をひらく | 観察は視覚だけでなく、音・香り・手ざわりでも育つ |
| 小さな気づきを書き留める | 気づいたことを日記やメモに残すことで、感覚が鋭くなる |
AIが当たり前のように隣にいる時代になって、
「人間にしかできないことは何だろう」と、ふと考えるようになりました。
そんなときに出会った、鈴木俊貴さんの言葉。
観察することの力強さや、そこに宿る可能性に、心から共感しました。
ChatGPTにはできないこと。
それは、目の前にある小さな変化に気づく“観察”という営みなのかもしれません。
これからも、自分は庭木や畑の変化に耳を澄ましながら、
そして人との対話の中でも、沈黙に寄り添いながら、
“観察力”を育てていきたいと思います。
今日も佳き日に
コーチミツル
#観察力 #鈴木俊貴さんに学ぶ #ChatGPTとの違い #自然から学ぶ #五感を育てる #気づきの力 #コーチングの本質