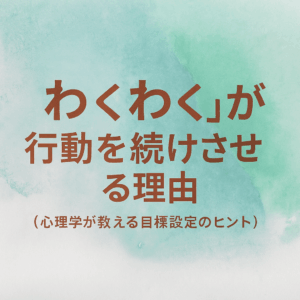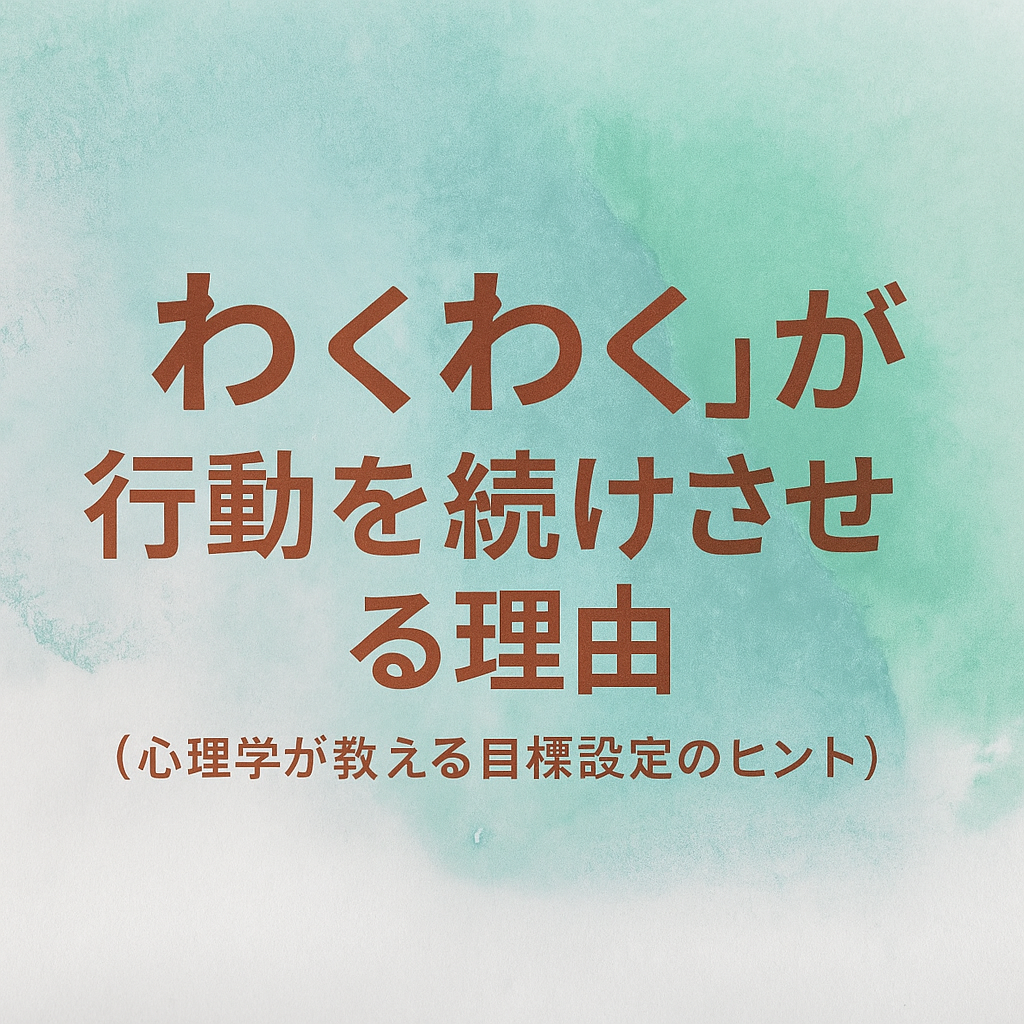
やらないといけない、より「やってみたい!」
目標を立てるとき、「期限を決めて」「数値で測れるように」といったアプローチはよく知られています。
たしかに、そうした“目標設定の技術”は大切です。けれど、それだけで人は動き続けられるでしょうか?
最近、自分の体験を振り返って思うのです。
行動を続けてこられた理由の根っこには、**「わくわく感」**がいつもあったということに。
「わくわく」は単なる気分ではない
心理学の世界でも、こうしたポジティブな感情が行動を支える力になることが多くの研究で示されています。いくつか代表的な理論を紹介します。
✅ 自己決定理論(Self-Determination Theory)
エドワード・デシとリチャード・ライアンによる「自己決定理論」では、
人が何かに本気で取り組むには「自律性」「有能感」「関係性」の3つの欲求が満たされている必要があるとされています。
中でも鍵となるのが、自分の内側から湧いてくる「やりたい」「面白そう」といった内発的動機づけ。
この“わくわく”が、報酬や評価などの「外からの動機」よりも、はるかに強い力を持つとされています。
✅ ポジティブ感情の拡張力(Broaden and Build Theory)
心理学者バーバラ・フレドリクソンは、ポジティブな感情が私たちの認知を広げ、創造性や柔軟性、レジリエンス(回復力)を高めると説きました。
わくわくするような目標に取り組むとき、私たちは視野が広がり、新しいアイデアが湧き、困難にも前向きに立ち向かえるようになります。
✅ 希望理論(Hope Theory)
リック・スナイダーによる希望理論では、目標達成の鍵として次の3要素が挙げられています。
- ゴール(目標)
- パスウェイ(達成までの道筋)
- エージェンシー(やり抜く力)
この中で、わくわく感やポジティブな未来像が「エージェンシー(やる気の火)」を育てるとされています。
実際、「わくわく」から始まったことは続いている
自分自身のことを思い返してみても、この理論はとても納得できます。
たとえば、筋トレを始めたきっかけは「ターザン」という雑誌の“脱げるカラダづくりコンテスト”。
写真入りで自分が掲載されたら…と思うと、なんだかニヤけてくるような気持ちがありました。
結果は2年連続で落選。でも、いまもトレーニングは続けています。
「やらないといけない」と思っているわけではなく、「やってみたい」が今も残っているからこそ、継続できているのだと思います。
また、作詞を始めたのも、今は亡き親友が「一緒に唄を作ってそれを歌いたい」と言ってくれたことがきっかけでした。
彼が自分の言葉を歌っている姿を想像したら、心がウキウキして。
結果的に、その詞は彼の最初で最後の代表作のひとつとなりましたが、いまも自分の大切な作品になっています。
数値より、心が動いたかどうか
目標を設定するとき、一般的なコーチングのフレームワークももちろん有効です。
でも、その前にこう自分に問いかけてみてほしいのです。
「この目標、考えただけで、ちょっと心が躍る?」
行動を続けるエネルギーは、いつだって“気持ちが動いた瞬間”に宿るのだと思います。
もし今、何かを続けられずにいるなら、やり方ではなく、**「気持ちが動く目標かどうか」**を見直してみるといいかもしれません。
あなたの今の目標――想像すると、心は動きますか?
「やってみたい!」と思える気持ち、大切にしていますか?
今日も佳き日に
コーチミツル
#わくわくする目標 #ポジティブ心理学 #自己決定理論 #内発的動機づけ #行動の継続 #HopeTheory #CoachMitsuruブログ #WellBeing #コーチング実践