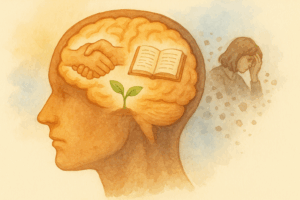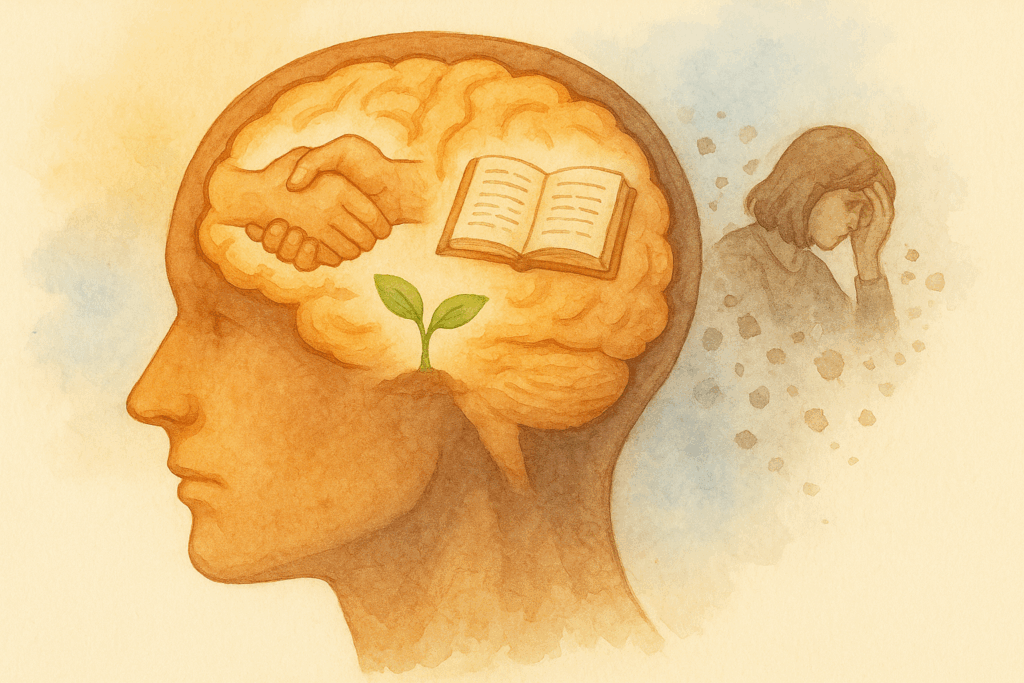
「忘れたいのに、忘れられない」
「忘れたくないのに、いつの間にか思い出せなくなっていた」
そんな経験、誰しもあるのではないでしょうか。
私たちの脳は、日々さまざまな情報を受け取りながら、必要なものを残し、そうでないものは少しずつ手放していくようにできています。これは脳が私たちを守るための、いわば“やさしいしくみ”です。
けれど自分は最近、「忘れずにいること」が人生にとってどれほど大切かを、あらためて感じるようになりました。
脳はなぜ忘れるのか? 〜エビデンスから見える仕組み〜
私たちの記憶は、海馬(かいば)という脳の器官で一時的に保存され、その後側頭葉の大脳皮質に移されることで長期記憶になります。
けれどこのプロセスで、脳は「これは今後も必要か?」と何度も判断を下しています。
実は、思い出さない記憶は、脳が“不要”と判断して自然に薄れていくのです。
逆に言えば、何度も思い出したり、感情を伴って記憶されたことは、長く残るようになっています。
この現象を「再固定化(Reconsolidation)」と呼びます。
そして、もう一つ大切なこと。
脳は「ネガティブな記憶」ほど強く、長く残す傾向があります。これは、危険から身を守るために必要な働きです。
ですがそれが「苦しい思い出」としていつまでも心に居座ってしまうこともあるのです。
忘れることは、悪いことじゃない
時には、「思い出すとつらくなる記憶」もあります。
そんな記憶は、無理に向き合うのではなく、少しずつ距離を取るのがいいのかもしれません。
実際、近年の研究では、意識的に「思い出さない」選択をすることが、記憶の消去や弱化につながることが示されています(Anderson & Green, 2001年)。
これは「抑制的想起」といって、過去の辛い記憶と上手に付き合うための、脳の大切な機能のひとつです。
でも、「忘れない」ことにも力がある
一方で、感謝の記憶や、自分が誰かに救われた瞬間の記憶、または何かを学んだ体験は、人生を豊かにしてくれます。
心理学では、「ポジティブな自己物語(Positive autobiographical narrative)」を持つ人ほど幸福度が高いことが分かっています。
つまり、自分にとって意味のある過去を、あたたかく思い出すことができる人は、幸せを感じやすいのです。
自分自身、過去の過ちや後悔を経て、ブログでも「それが自分の成長の証だった」と綴ってきました。
(▶︎参考:「二十歳の頃の過ち」https://coach-mitsuru.com/archives/713)
傷つけてしまった人への思い、あの時の自分の未熟さ…
それらを忘れずに心に持ち続けることで、「これからの自分はどう生きるか」を考えられるようになったのです。
幸せな人生に必要な「記憶」とは
幸せになるために必要なのは、「何もかも忘れること」ではありません。
むしろ大切なのは、どんな記憶を心に残し、育てていくかではないでしょうか。
感謝されたこと。
大切な人との時間。
誰かに許されたこと。
こうした記憶を忘れないように、大切に抱きしめていくこと。
それは人生を、じんわりと温めてくれる灯火のようなものだと感じています。
「忘れること」も、「忘れないこと」も、
どちらも私たちが前に進むための大切な働きです。
辛い記憶は、無理に思い出さなくていい。
でも、感謝や学びの記憶は、できるだけ忘れずにいたい。
それが、過去と未来をつなぐ“優しい記憶の選び方”なのかもしれません。
今日も佳き日に
コーチミツル