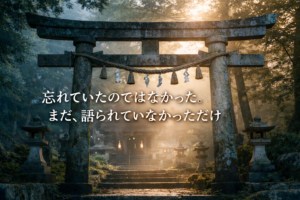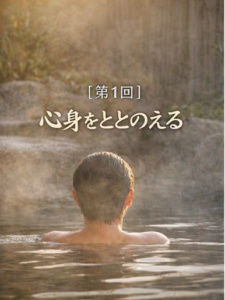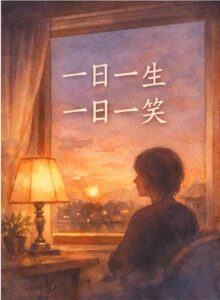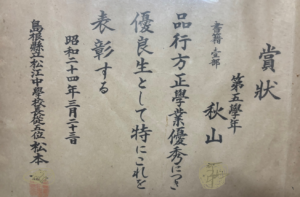エンジンがある車が好き
車を運転するときに感じる楽しさは、人それぞれです。
静かでなめらかな走りを好む人もいれば、アクセルを踏み込んだ瞬間にエンジンが反応してくれる「音」や「振動」にこそ魅力を感じる人もいます。自分はまさに後者で、エンジン音そのものが運転の楽しみになっています。
近年、環境に優しいとされるEV(電気自動車)が広がってきましたが、自分は静かで快適な反面、どこか「物足りなさ」を感じてしまうのは、きっとエンジンの存在感がないからだと思います。
EVのメリットと課題
EVは確かに優れた点があります。
- 走行中に排ガスを出さない
- 静かでスムーズな加速
- モーターによる瞬時のトルク
しかし課題も見えてきました。
- 冬場に航続距離が大幅に落ちる
- 充電インフラがまだ整っていない
- バッテリーの寿命とリサイクル問題
- 発電段階でのCO₂排出:走行時に排出はなくても、電源が火力発電由来であれば製造・充電の過程で温室効果ガスは発生します。つまり「全く排出しない」わけではなく、発電方法によって環境性能は大きく変わるのです。
EVが本当に環境に良いかどうかは、電源構成やバッテリーのライフサイクル全体を含めて考える必要があると感じています。
水素燃料電池(FCEV)
次に登場するのが「水素燃料電池車(FCEV)」です。
水素を電気に変えてモーターを動かすため、排出するのは水だけ。EVの「静かさ」を持ちながら、航続距離や充填時間の面でガソリン車に近づけるのが魅力です。
ただし、FCEVも「モーター駆動」なので、運転感覚はEVに近く、エンジンの鼓動を求める人には少し物足りない部分が残ります。
水素内燃機関(H₂-ICE)
そこで期待しているのが、水素を燃やして走るエンジンです。
仕組みは従来のガソリンエンジンに近く、違いは燃料が「水素」になること。排出は基本的に水とごくわずかなNOxのみ。
- これまで培われたエンジン技術を生かせる
- 既存の部品メーカーも形を変えて生産可能
- アクセルに反応するエンジン音とドライビングフィールが残せる
つまり、環境対応をしつつ「エンジン文化」を守る道がここにあると感じます。
日本企業の取り組み
日本の自動車メーカーは、それぞれ独自のアプローチで未来のエンジンに挑戦しています。
- トヨタ自動車
水素燃料電池車「MIRAI」を市販化しながら、同時に「水素内燃機関」にも挑戦。耐久レースに水素カローラを投入し、実走での改良を重ねています。さらに長年培ったハイブリッド技術(プリウスに代表されるHEV)も、EV一辺倒ではない多様な選択肢として世界的に評価されています。 - ホンダ
FCEV「クラリティ・フューエルセル」の市販を経て、次世代モデルも開発中。さらに軽量・高効率なハイブリッド車を広く展開し、環境性能と実用性の両立を進めています。 - マツダ
マツダは独自の「ロータリーエンジン」を復活させ、EVの航続距離を伸ばす**発電用エンジン(レンジエクステンダー)**として搭載しました。エンジンのコンパクトさを活かし、電動化と内燃機関の共存を目指すユニークな取り組みです。
これらの事例は、日本の自動車産業が「電池だけ」や「エンジンだけ」に偏らず、多様な選択肢を同時に追求していることを示しています。
比較表
| 方式 | 魅力 | 課題 |
|---|---|---|
| EV(電気自動車) | 静かで瞬発力あり。都市向け。 | 航続距離、充電、バッテリー処理、発電段階でのCO₂排出。 |
| FCEV(水素燃料電池) | 水素で発電し、排出は水のみ。長距離OK。 | 高コスト、インフラ整備。音・鼓動は薄い。 |
| 水素内燃機関 | エンジン音と走りの楽しさを継承。産業構造も活かせる。 | NOx制御、燃焼制御の難しさ、インフラ整備。 |
| ハイブリッド | エンジンとモーターの良いとこ取り。燃費性能◎。 | バッテリー依存が残る。完全ゼロ排出ではない。 |
コーチミツルの結論
どの方式も一長一短がありますが、自分は水素内燃機関に最も惹かれています。
理由は単純で、エンジンの音と鼓動が好きだから。そしてもう一つは、これまでの自動車産業の技術や地元の部品工場の力をそのまま未来に引き継げるからです。
EVや燃料電池も選択肢として必要ですが、「音を楽しみたい人」「エンジン文化を残したい人」にとって、水素エンジンは大切な可能性を秘めていると思います。
あなたにとって「車の楽しさ」とは何でしょうか?
静かな走りでしょうか、それともアクセルに応えるエンジンの響きでしょうか?

今日も佳き日に
コーチミツル
#水素エンジン #燃料電池車 #ハイブリッド車 #トヨタ #ホンダ #マツダ #ロータリーエンジン #カーボンニュートラル #エンジンの未来 #車好き