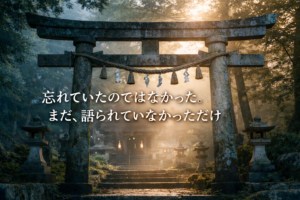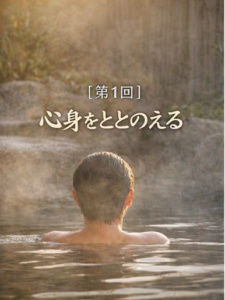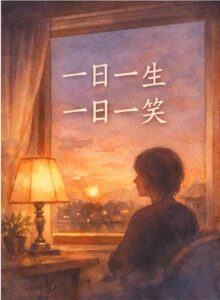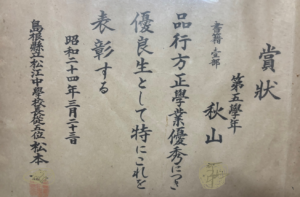種からの挑戦、はじめての夏
今年から、本格的に自然栽培に取り組み始めました。
肥料も農薬も使わず、草もなるべく抜かず、
「自然の力に任せて、野菜たちが本来の力で育っていく姿を見てみたい」
そんな思いからのスタートでした。
これまでのように苗を買うのではなく、種から育てるという試みにも挑戦しました。
発芽や根付きには時間がかかりましたが、少しずつ育っていく様子に心が躍りました。
ところが——
今年の夏、キュウリやナスはほとんど実をつけず、トウモロコシも夏前まで元気だったのが、次第に枯れていきました。
唯一、なんとか収穫できたのは小さな人参と夏大根くらい。
「どうしてだろう?」
そう考えていたとき、ふと過去の記憶がよみがえってきました。
「一雨降った後、野菜が一気に大きくなる」
そんな印象が、頭の中にずっと残っていたのです。

気づいたのは、“雨”の違い
そこで2025年の春から夏にかけて、松江市で実際にどれくらい雨が降ったのかを調べてみました。
以下は、気象庁のデータをもとに整理した「1mm以上の降水があった日数」です。
| 月 | 2025年(雨の日数) | 平年(1991〜2020年平均) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 14日 | 約13〜14日 | 平年並み |
| 6月 | 20日 | 約17〜20日 | 梅雨期らしい雨量 |
| 7月 | 3日 | 約17〜20日 | 極端に少ない(干ばつ) |
一見、5.6月は雨の日数そのものは平年と大きく変わらなかったようにも思えますが、
注目すべきは**「7月の雨日数がたったの3日」**という点です。
これは、例年の1/6程度しか雨が降らなかったことを意味しています。
種まきと雨のタイミングが、すれ違っていた
今年は、はじめての種まき。
当然、苗よりも成長が遅く、6月の梅雨の時期に思うように育ちきらず、
雨の恩恵を受けられたのはごく一部の野菜だけでした。
そして、ようやく少し成長してきた7月。
ここで待っていたのは、極端な高温と、ほとんど雨の降らない日々。
ナスやキュウリ、トウモロコシなどの果菜類は、
ちょうどこの時期に水を欲しがるにもかかわらず、土の中には水分がほとんど残っていなかったのです。
土は乾き、光合成も滞り、実がつかない。
そんな「水の断絶」を、今年の野菜たちは経験していたのだと思います。
学びから、次の一手へ
自然栽培では、「自然に任せる」ことが大切です。
けれど、今回のように極端な偏りがある気候の年には、
「必要なときに手を差し伸べる」という視点も大切だと感じました。
幸いなことに、うちには井戸水があります。
そこで今年の夏を経て、**スプリンクラー(ホースの先につけるタイプ)**を導入することにしました。
- 雨が極端に少ない時期には、ある程度しっかりと水を与える。
- 水やりは野菜に害を与えるどころか、干ばつ下では命を支える必須の手段になる。
- 井戸水という資源を、自然と共に生きるために活かしていく。
自然に対して「口を出さない」のではなく、
必要なときに「力を貸す」こともまた、育てる側の役目かもしれません。
自然とともに育つには
来年また、種からの挑戦をするときには、
成長のタイミングと雨のリズムを見極めながら、
「任せる」と「支える」のバランスを大切にしたい。
自然はいつも、厳しくも優しく教えてくれます。
あなたが育てている何かのために、
“水を与えるタイミング”が必要なときがあるとしたら、どんな時ですか?
今日も佳き日に
コーチミツル
#自然栽培 #雨のリズム #干ばつ対策 #スプリンクラー導入 #井戸水活用 #野菜づくりの学び #気象データで考える #コーチミツルブログ