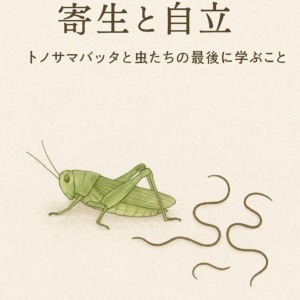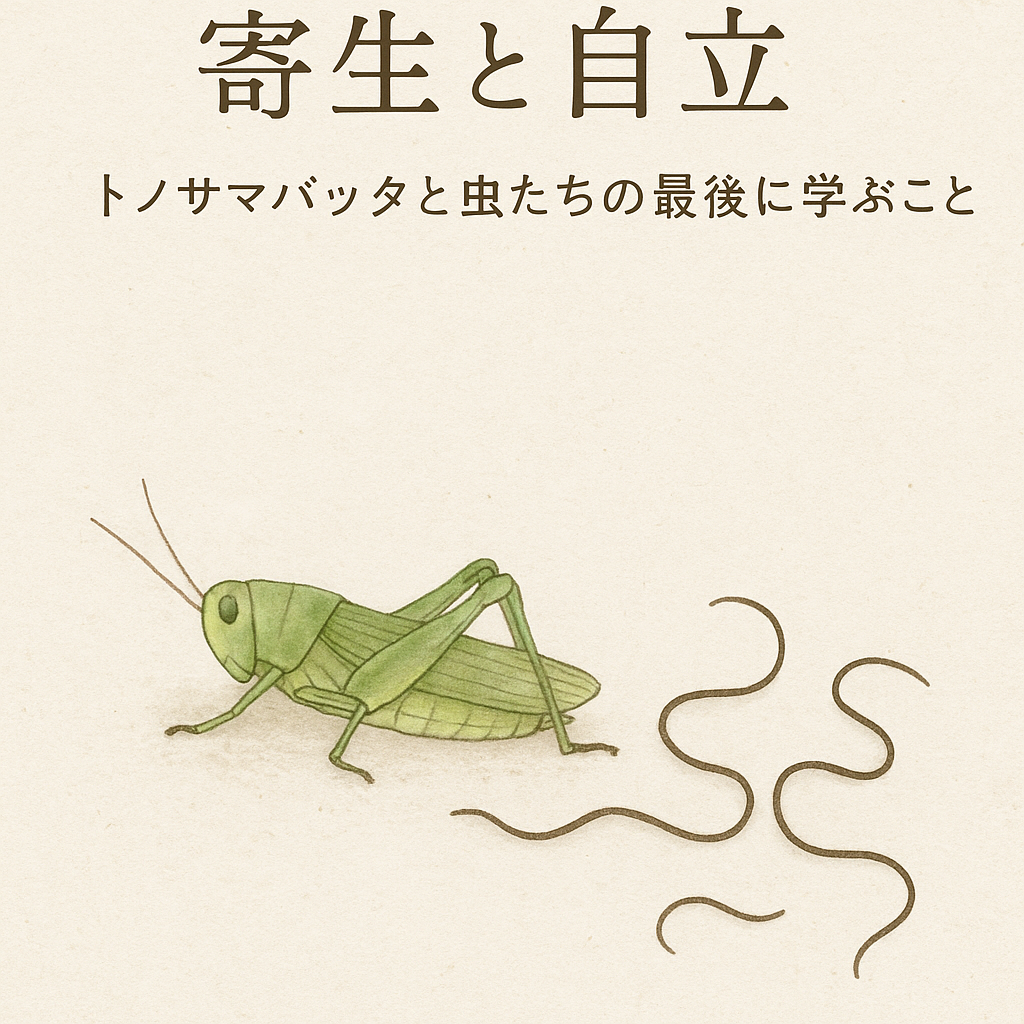
今日、買い物から帰ってきたときのことです。
車庫で荷物の出し入れに気を取られていた自分は、足元のトノサマバッタをうっかり踏んでしまいました。
「ごめんね…」とつぶやきながらしゃがみ込んだそのとき、思わぬことが起きました。
バッタの体から、針金のように細長い虫が3匹、大・中・小の順に這い出してきたのです。
その光景に、自分はしばらく言葉を失いました。
虫たちは数分のあいだ体をくねらせながら動いていましたが、やがて静かに動かなくなっていきました。
とてもショッキングな出来事でしたが、自然の厳しさや命のつながり、そして「生き方」について静かな問いを感じる体験でした。
ひとつに頼りきっていると、ともに倒れてしまう
あとで調べてみると、あの虫たちは「ハリガネムシ」と呼ばれる寄生虫でした。
バッタの体の中で生きていた彼らは、宿主が命を失ったことで、自分たちも生きられなくなってしまったのです。
その姿を見て、自分の中に自然とこんな思いが浮かびました。
「たった一つのものに、すべてを預けて生きていると、それがなくなったときに一緒に倒れてしまうこともあるんだな……」
「寄生」と「共生」そして「自立」のちがい
自然界にはさまざまな関係があります。
寄生:相手に頼りきって、自分だけが得をする関係。
共生:お互いに助け合いながら、両方が恩恵を受ける関係。
自立:誰かに支えてもらうことがあっても、基本的には自分の足で立とうとする生き方。
今回見た寄生虫とバッタの関係は、まさに「寄生」そのもの。
バッタの体を使い、バッタの命の終わり、最終的には水辺に導いて死に至らせ、自分たちは次の宿主を探す――そんな仕組みを持っています。
宿主にもメリットがあるの? という素朴な疑問
実は、自然界ではまれに「寄生」とされる関係の中にも、宿主にとってわずかなメリットが生まれることがあるそうです。
たとえば人間の場合、腸内にいる一部の寄生虫がアレルギーを抑える働きをするといった研究もあり、これを「衛生仮説」と呼ぶそうですす。
また、種全体の進化の視点から見ると、寄生されやすい弱い個体が淘汰され、強い遺伝子が残る仕組みにつながる、という考えもあります。ですが、「栄養を奪われ、脳を操られ、水辺に誘導されて死ぬ」――そんな命の消耗戦のようにも感じられます。
今回のようなハリガネムシとトノサマバッタの関係には、バッタにとってのメリットはほとんどないそうで、虚しさやはかなさを感じずにはいられません。
ポートフォリオ的な生き方って?
このできごとを見ながら、自分はふと「ポートフォリオ」という言葉を思い出しました。
「ポートフォリオ」とはもともと金融の用語で、ひとつに集中せず、複数に分散しておくことでリスクを抑える考え方です。
これを人生にも応用してみると、たとえばこんな生き方になります:
- 仕事も、複数の関わりや収入の柱を持っておく
- 人間関係も、家族・地域・趣味・学びなど、いくつかの居場所を持つ
- 心の支えも、自然や音楽、言葉や体を動かすことなど、多面的にしておく
もし、ひとつが失われても、他の支えが自分を立たせてくれる――
そんな安心感のある暮らし方が、「ポートフォリオ的な生き方」なのだと思います。
自分も、コーチング・音楽・自然農・地域活動など、いくつかの軸を持っていることで、折れずにやってこられたように感じています。
小さな命がくれた、大きな気づき
今日、車庫でうっかり踏んでしまったバッタ。
そして、その体から出てきた3匹のハリガネムシたち。
その命の終わりの場面に立ち会いながら、
「生き方」や「頼り方」、そして「命のあり方」について、深く考えさせられました。
最後に、そっと問いかけてみます
それがなくなった時、あなた自身が立ち続ける生き方があるとしたら、どんな生き方ですか?
完全にひとりで生きることはできません。
でも、支えをいくつか持っておくことは、これからの時代を穏やかに乗りこなすためのヒントかもしれませんね。
今日も佳き日に
コーチミツル
#CoachMitsuru #トノサマバッタ #ハリガネムシ #自然からの気づき #寄生と自立 #共生と進化 #ポートフォリオ的生き方 #命のメッセージ #自然からの学び #ポートフォリオ的生活 #命が教えてくれたこと #優しく問いかける