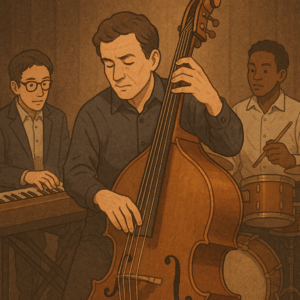「出るところ」と「抑えるところ」――
このバランスは、音楽でも日常でも、人との関係でも、とても大切なテーマです。
ジャズのセッションに参加していると、あるルールに気づきます。
それは、「誰かがソロを取るとき、他の人は引く」という暗黙の了解です。
たとえば、ベースのソロのとき。
普段は伴奏に徹しているベースが主役に回ると、周りのピアノやドラムは音を弱めて、ベースが浮き出るように演奏します。
そうやってお互いに気を配り合い、誰かが目立つときはそっと支える。
それが自然に行われるのが、ジャズの美しさであり、人の配慮の形でもあると感じています。

メゾフォルテばかりの演奏は、平坦な音楽になる
実は、自分自身の演奏にも思うところがあります。
どちらかというと、自分は「出る」ことより「抑える」方を選びがちです。
場の空気を読みすぎて、いつも無意識に遠慮してしまうことが多いのです。
でも、演奏というのは、ずっとメゾフォルテ(中くらいの音量)で演奏し続けると、起伏がなくなってしまう。
抑えるところが美しく響くためには、出る場面があるからこそ。その抑揚が音楽の魅力になります。
これは、仕事でも人間関係でも同じことが言えるように思います。
経験談:出なかったことを後悔した場面
少し前に、社会人として高校生に経験談を伝える機会がありました。
実際のところ、自分にも話せることはたくさんあったのですが、その場に“やりたい人”がいたので、「じゃあ、どうぞ」と身を引いてしまいました。
でもあとで思いました。
自分が話していた方が、その高校生にとってはもっと参考になったかもしれない、と。
空気を読んだつもりだったけど、結果的に伝えるべきものを伝えずに終わってしまった――。
あの時は、“出る”ことが相手のためだったのではないかと、今でも少し後悔しています。
抑えることは悪くありません。
でも、それが「相手にとっての機会を奪う」ことになるのだとしたら、出る勇気も必要なのです。

“主役を立てる”ための空気の読み方
ドラマの中で主人公が輝くには、脇役の存在が欠かせません。
脇役がその場にふさわしい間合いや表情を見せるからこそ、主人公のセリフが生きてくる。
だからこそ、「出る」と「抑える」は対立するものではなく、どちらも必要な“役割”だと感じます。
でも一方で、自分自身はこうも思っています。
「出ない」ことが癖になってしまうと、いつまでも主役になれない。
自分を抑えることに慣れすぎると、「出る」ことに恐れを感じるようになってしまうのです。
空気を読むとは、どういうことか?(心理学的な背景)
心理学では、こうした力を「社会的知性(social intelligence)」と呼びます。
これは「他者の感情や意図を察し、それに適切に対応できる力」のことです。
スタンフォード大学のダニエル・ゴールマンは、感情的知性(EQ)の中でも「社会的スキル」や「共感力」が、リーダーシップや人間関係の質に強く関わると述べています。
また、東京大学の中原淳教授は、仕事の現場での“気づき”の多くは「暗黙知(Tacit Knowledge)」によって成り立っていると指摘します。
これはまさに、“場の空気”を読む力そのものです。
でも、それを“過剰”に働かせてしまうと、自分の意見や存在感を出せなくなってしまう。
僕もまさに、そのジレンマを抱えてきました。
あなたの“空気を読む力”をセルフチェックしてみよう
以下の10項目のチェックリストで、自分の“空気を読む力”を見える化してみませんか?
1つ1つ、5点満点で自己評価してみてください。
| No | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 相手の表情や声のトーンから感情を読み取るのが得意だ |
| 2 | 会話の輪に入るタイミングを自然につかめる |
| 3 | 会議や練習中に、発言すべきか黙るべきか判断できる |
| 4 | 他人が困っている時に、声をかけるか見守るか適切に判断できる |
| 5 | 自分の発言や行動が場にどう影響を与えるか想像できる |
| 6 | グループの中で誰が目立っていて、誰が引いているかに気づく |
| 7 | 自分の役割を状況に応じて変えることができる |
| 8 | 他人の話を遮らず、聴き役に徹することができる |
| 9 | 空気を読みすぎて自分の本音を言えないことがある |
| 10 | 自分の中で「今は出るべき」と感じてもブレーキをかけがちだ |
合計点の目安:
- 40点以上: 空気を読む力は十分。ただし出す場面を意識して練習を。
- 30〜39点: バランス感覚があるが、やや遠慮がち。場面ごとの判断力を磨くと◎
- 20〜29点: 空気を読む力は育ちつつある段階。意識的な練習で伸びます。
- 19点以下: 自己主張と協調のバランスを学ぶ段階。体験とフィードバックがカギ。
遠慮しすぎを脱するための実践法 ― “出る力”の育て方
● ソリューションフォーカスの“スモールステップ”
いきなり大きく出るのではなく、まずは「ほんの少し」音量を上げてみる。
ワンフレーズだけでも前に出てみる。
そうやって小さな成功体験を積み重ねることで、自分の中の“出る回路”が育っていきます。
● 「これは自分の番」と決めてみる
何も考えずに空気を読むだけでは、いつまでたっても出られません。
「この8小節は自分が主役」と決めておくと、不思議と演奏の気持ちも変わります。
● フィードバックをもらう
信頼できる仲間に、「もっと出てもよかった場面はあった?」と聞いてみましょう。
自分では見えていなかった“出るチャンス”に気づけるかもしれません。
● “出る”は貢献でもある
自分が音を出すことで、場が活きる。
そんなふうに“出る”ことを再定義してみてください。
抑えるだけが思いやりじゃない。出ることも、実は思いやりの一つです。
音楽と人生の「抑揚」を大切に
音楽においても、人生においても、「出る」と「抑える」の両方があってこそ、美しい抑揚が生まれます。
空気を読むことは素晴らしい力です。
でも、それに縛られず、時には自分の音を放つことも忘れないでいたい。
そうすればきっと、あなたの“音”も、まわりの“音”も、もっと豊かに響き合っていくはずです。
今日も佳き日に
コーチミツル
#空気を読む力 #出る勇気 #抑える美学 #ジャズに学ぶ #メゾフォルテ人生 #共感力 #社会的知性 #ソリューションフォーカス #成長のヒント #経験を語る
参考文献・エビデンス
- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
- 中原淳(2020)『職場の科学』プレジデント社
- Baron-Cohen, S. (2011). The Science of Evil. Basic Books.