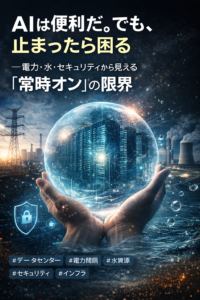ブログ内容を朗読しています(115.お茶事(おちゃごと)という家族の時間)
先日、職場でふと耳にした「お茶事(おちゃごと)」という言葉。それを聴いた瞬間、懐かしい記憶がふわっとよみがえりました。
小さい頃、家族で毎週のように過ごしていた、あの穏やかで和んでいた夜の時間。長い間、それは我が家だけの風習だと思っていましたが、どうやら出雲地方の古い家ではよく見られた習慣だったようです。
わが家のお茶事の風景
「お茶事」の想い出ですが、一番覚えているのが休み前の土曜ドラマがやっている時間帯でした。夕飯が済んで、みんなでテレビを見ているような、そろそろ眠る準備をする少し前の時間。
コタツの上には、皿に載せた旬の赤かぶや大根の漬物(私たちは「漬けもん」と呼んでいました)、木をくりぬいたような容器にお菓子が並び、大人たちは煎茶、子どもたちは番茶を飲みながら、家族でその日あった出来事を語り合います。
忘れられないのは、母が常に急須を持っていて、誰かの湯飲みが空になると、まるでわんこそばのようにすぐにお茶を注ぎ足してくれたこと。次々と注がれる湯気立つお茶に、会話も自然と続いていきました。
小学校高学年になると、ちょっと背伸びして、ネスカフェのインスタントコーヒーにクリープと砂糖をたっぷり入れて飲むようになったのも当時の思い出です。今のような本格的なコーヒーは家に無かった時代、インスタントが「大人の味」だったんです。
出雲地方とお茶文化
「お茶事」ですが、辞書で調べてみると茶事(さじ)という読み方もあり、茶道の正式な行事を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、私が体験していたのは、もっと生活に根ざした、家庭でのささやかな団らんのこと。
出雲、特に松江は、古くからお茶文化が息づく地域です。江戸時代、松江藩の松平不昧公が茶の湯文化を庶民にも広め、抹茶と和菓子を楽しむ風習が生活の中に根付きました。
その流れをくむ形で、農村部の家庭でも気軽にお茶を囲む習慣が自然と生まれていったのかと思います。作業の合間の小休憩のことを出雲地方ではタバコすると言ったりもしますが、出雲地方で「お茶事」と呼ばれるこうした時間は、格式ばらず、暮らしに寄り添った団らんの場だったのだと思います。
お飾らない会話と安心感
この「お茶事」の時間は、ただの飲み物タイムではありませんでした。
何気ない話、学校の出来事、ちょっとした愚痴。誰かが話し始めると、他の誰かが自然に話を続けて、止まらないおしゃべりの輪が生まれます。親父は聴いてニコニコ笑ってばっかりだったかなあ。
不思議と、この時間だけは飾らない本音がポロッと出る。叱られることもなく、否定もされない、そんな安心の中で育まれたコミュニケーション。これが、子ども心にとても心地よかったんです。
もしかすると、なかなかおねしょが治らなかったのはこの寝る前のお茶のせいかもしれません(笑)。でもそれすらも、嫌な思い出として残っていないというのは、この「お茶事」が本当に温かく、楽しい時間だった証なんだと思います。
今では、
「お茶事」という言葉も、習慣も、耳にすることも少なくなりました。家族全員が集まり、ゆっくりとお茶を飲みながら話をする時間も、現代では貴重なものかもしれません。
けれど、あの頃の「お茶事」は、確かに私の心の奥にあって、今も生き続けていると思います。
飾らない言葉で、家族と本音で語り合えた時間。
ただお茶を飲むだけなのに、心が満たされていくような、不思議な時間。
そんな「お茶事」を、これからも心の中に大切に思い続けたい。
そして、いつかまた誰かと、あのような時間を共有できたらいいなと願っています。
今日は昭和の子供の頃の思い出をお伝えしました。

今日も佳き日に
コーチミツル