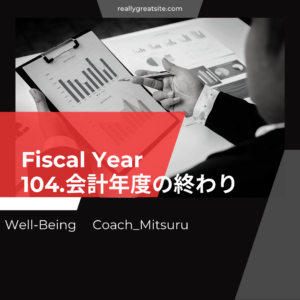今日は、3月31日で、
日本で言えば、年度の終わりということで一区切りとなります。自分は、経理の仕事をずっとしていたので、この3月31日の年度決算は、3月の中旬ごろから5月の連休前までかなりheavyな仕事を何年も続けていて、その上、途中から四半期決算も入ってきて、3ヶ月に1回は仕事の波がやってくるという感覚でした。
特に3月末の年度決算は、全ての経理処理(税務処理も含)を期限までに行わないといけないし、間違いが途中で発生したら、その間違えた処理まで戻って、次工程の経理処理をやり直さなければならないこともあり、精神的にもシビレる期間でした。なので、子供たちの入学式は仕事がピークなのでなかなか行くことができなかったと記憶しています。そんな、年度決算の考え方、いわゆる、日本で4月から翌年3月を一区切りとしているのは世界的に一般的なことなのかという疑問がわいてきました。
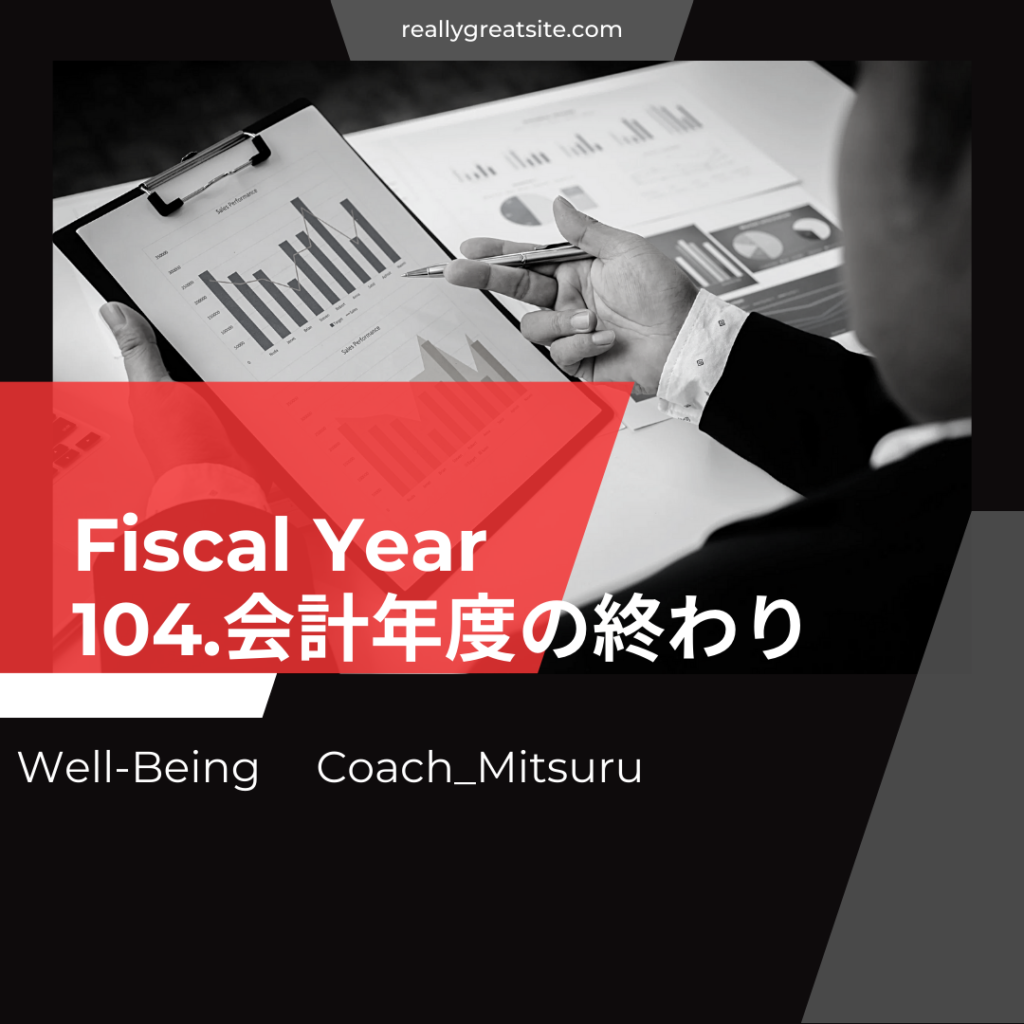
そこで、Wikipediaで世界の会計年度について調べてみました。
| 会計年度 | 採用国 |
|---|---|
| 1月 – 12月制 | 中華人民共和国・韓国・台湾(中華民国)・フランス・ドイツ・オランダ・ベルギー・スイス・ロシア・南アメリカ諸国など |
| 4月 – 3月制 | 日本・インド・パキスタン・イギリス・デンマーク・カナダなど |
| 7月 – 6月制 | フィリピン・ノルウェー・スウェーデン・ギリシア・オーストラリアなど |
| 10月 – 9月制 | タイ・ミャンマー・アメリカ・ハイチなど |
意外だったのは、4月~3月の会計年度の国が少ないことと、今一番日本に影響力のあると言われているアメリカが10月-9月の会計年度だったこと。
また、会計年度について日本の歴史を紐解くと、こんなことが書かれていました。
こうしてみると、明治の時代は、かなりいろいろと混乱と言いますか、会計年度の動きがあったのだなと感じます。何でこのように動きがあるのかと思ってWikipediaで調べてみると、最終的に4月~3月制になった理由が、明治15年(1882年)の壬午事変(じんごじへん)により、翌年から大日本帝国海軍の拡充計画が進んだため、財政赤字の穴埋めの必要から明治18年度(1885年度)の酒造税を明治17年(1884年)度に繰り入れしてしまい、翌年度の税収を繰り入れてしまったこの状況を改善するには、明治19年(1886年)度より酒造税の納期(第1期が4月)に合わせて年度変更するほかに方法がないことになり、明治17年(1884年)10月に「4月 – 3月制」の導入が決定され、明治19年(1886年)4月から実施されたとのことでした。
そこから落ち着いて今まで続いているのが、4月~3月制ということで、
同じ年度の国を見てみるとその中でも先進国としてのイギリスの存在が特に気になります。ちなみに、イギリスは、19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、アメリカ、カナダ、オーストラリア、インド、エジプト、東南アジア諸国、アフリカ諸国など多くの地域を植民地支配していたということで、その影響力も会計年度に繋がっているのかなと想像してしまいます。
もしかしたら、この明治19年頃というのが、イギリスと日本が近くなってきている時代ではないかと思い、調べてみると、
明治時代におけるイギリスと日本の関係は、
外交、経済、技術、文化など幅広い分野で緊密であり、外交では、1858年に日英修好通商条約が締結され、両国の外交関係が開設、その後1902年に日英同盟が結ばれ、ロシアに対抗する協力体制が敷かれたので、もしかしたら、会計年度もイギリスに合わせて、各国の財政面での状況が把握できるようにしたのかなあなんて思ったりした次第です。
今日は、会計年度について想像を膨らませてみました。もしかしたら、今でも財政面ではイギリスの影響を受け続けているのかもしれませんね。(笑)
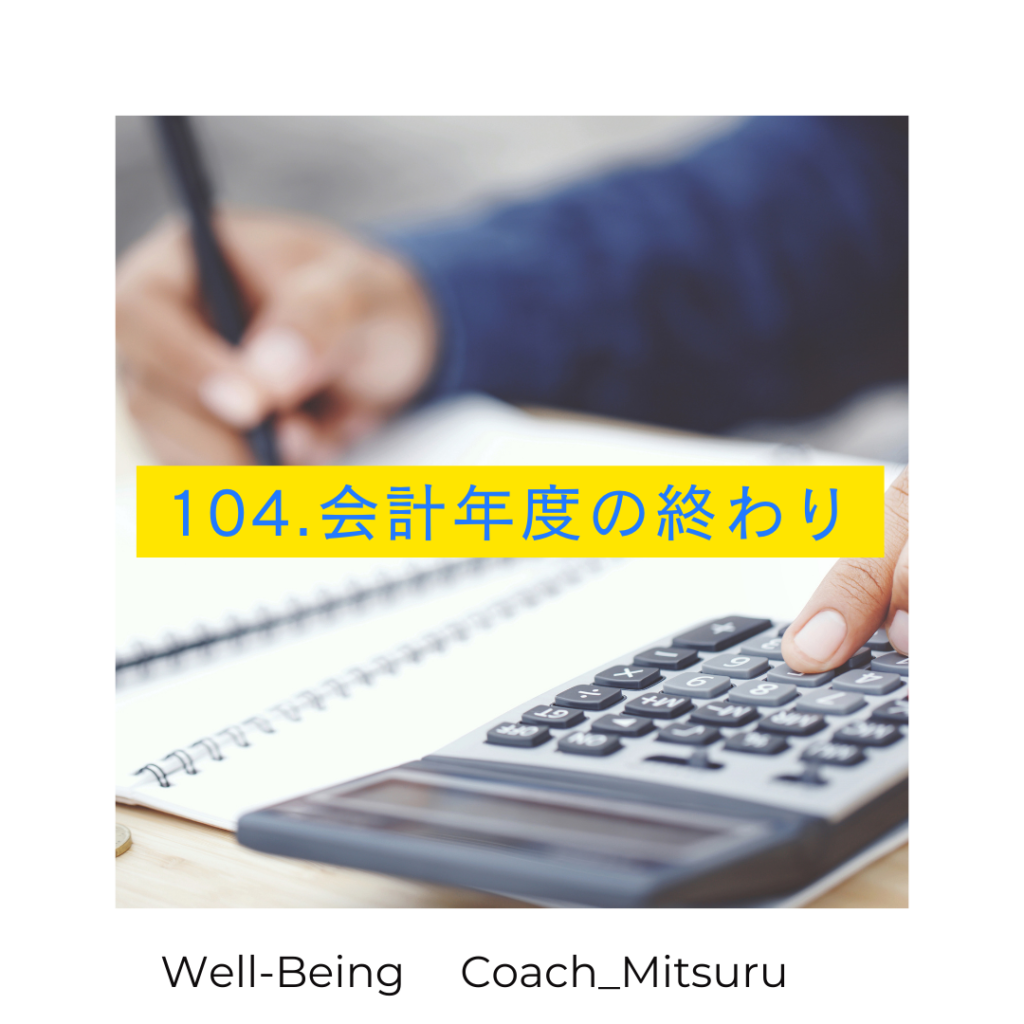
今日も佳き日に
コーチミツル