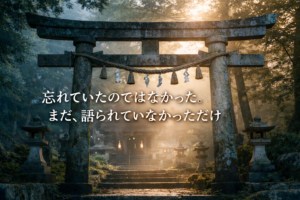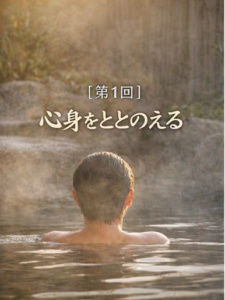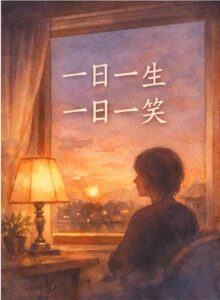愛機・Bach Stradivarius 180ML ― アーリー・エルクハートとの出会い
自分にとって特別な一本、Bach トランペット Stradivarius 180ML(シリアル43***)。
1969年頃に製造された、いわゆる「アーリー・エルクハート」と呼ばれる時代の楽器です。
この楽器との出会いは、ニューヨークで活動されていたジャズトランペッター 佐々木亮さん のYouTubeを見たとき。そこで吹かれていた音色と、楽器の美しさに一目惚れしました。どうしてもこの一本が欲しくなり、お願いして譲っていただいたのです。
特に心惹かれたのは、バルブ(ピストン)ケーシングがツーピース構造になっていて、ゴールドとシルバーのコントラストが美しく際立っていたこと。

この仕様はマウントバーノン時代の設計を継承したもので、当時の職人さんのこだわりが今も伝わってくるように感じます。見た目の存在感と同時に、音色にも不思議な説得力を与えてくれる部分です。
この楽器を実際に使い始めたのは、2023年8月から。そこからコンボやビッグバンドで演奏する機会が一気に増え、音楽活動の広がりを感じています。
そして、音を出すたびに少しずつ馴染んでくれている実感があるのも、この楽器と過ごす大きな喜びのひとつです。
Bach トランペットの世代と特徴
Bach トランペットには、いくつかの大きな世代があります。以下の表にまとめてみました。
| 世代 | 製造年代 | 特徴・音色の傾向 |
|---|---|---|
| マウントバーノン(Mount Vernon) | 1953〜1965年頃 | ・ニューヨーク州マウントバーノン工場 ・手工的仕上げで独自性が強い ・音は柔らかく豊かで「黄金期」と呼ばれる |
| アーリー・エルクハート(Early Elkhart) | 1965〜1970年頃 | ・移転直後でバーノンの職人技術を継承 ・深みある音色+レスポンスの良さ ・ヴィンテージの最高峰とされる |
| 後期エルクハート(Later Elkhart) | 1970〜80年代前半 | ・生産拡大により個体差が増える ・音は明るめで現代的 |
| 現行(Monopoli〜現代製) | 1985年〜現在 | ・大量生産で安定品質 ・音は明るくパワフル ・標準機として定着 |
このように、マウントバーノンやアーリーエルクハートは古い世代でありながら独特の響きを持ち、しかもコンディションの良い個体は年々稀になっています。だからこそ、自分がこの一本に出会えたこと、そして譲っていただけたことに心から感謝しています。

憧れの音色に近づいて
同じ時代の楽器を使われていたのが、日本ジャズ界の重鎮 村田浩さん。
その音色は、ブルー・ミッチェルを彷彿とさせるような柔らかく優しい響きで、以前ライブを聴きに行ったときに強く心を揺さぶられました。自分の愛機もまた、その「温かさ」と「深み」を持っているように感じています。
そして、世界的に活躍する憧れの 黒田卓也さん は、さらに前の「マウントバーノン期」のBachを愛用されています。
マウントバーノンは数が少なく、しかも調子の良いものにはなかなか出会えません。
それだけに、このアーリー・エルクハートは自分にとって唯一無二の存在です。
新しい楽器との違い、そして「縁」
新品の楽器はもちろん素晴らしいものですが、ヴィンテージには「時間を重ねてきた深み」と「縁」のようなものを強く感じます。
この一本に出会えたことは、偶然ではなく、まるで導かれたような不思議な感覚がありました。新しい楽器を買うのとは違い、ヴィンテージは「待っていた相手に出会う」という喜びがあるように思います。
楽器は恋人のように
ヴィンテージ楽器というのは、ただの「道具」ではなく、まるで恋人のようなものだと思います。
出会い方やインスピレーション、その時の心の状態で「この一本だ」と感じる瞬間がある。
自分にとって、このトランペットはまさにそういう存在であり、音を出すたびに初心を思い出させてくれる大切な相棒です。
マウスピースのこと
楽器だけでなく、ラッパをする人にとってどうしても気になるのが「マウスピース」。
自分は現在 AR RESONANCE を使用しています。まだまだ思うような演奏には程遠いですが、このマウスピースとともに、自分の音を探しながら勉強しているところです。
✅ この愛機とともに、今後もジャズを楽しみながら勉強していきたいと思います。
今日も佳き日に
コーチミツル
トランペット #ジャズ #Bach #アーリーエルクハート #愛機紹介 #ジャズトランペット #ヴィンテージ楽器 #音楽のある暮らし #楽器との出会い