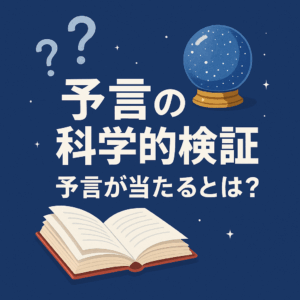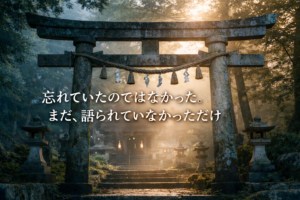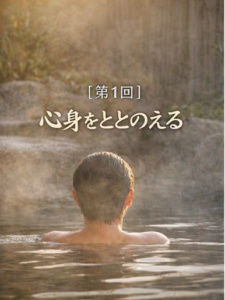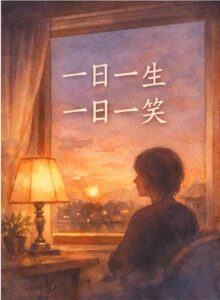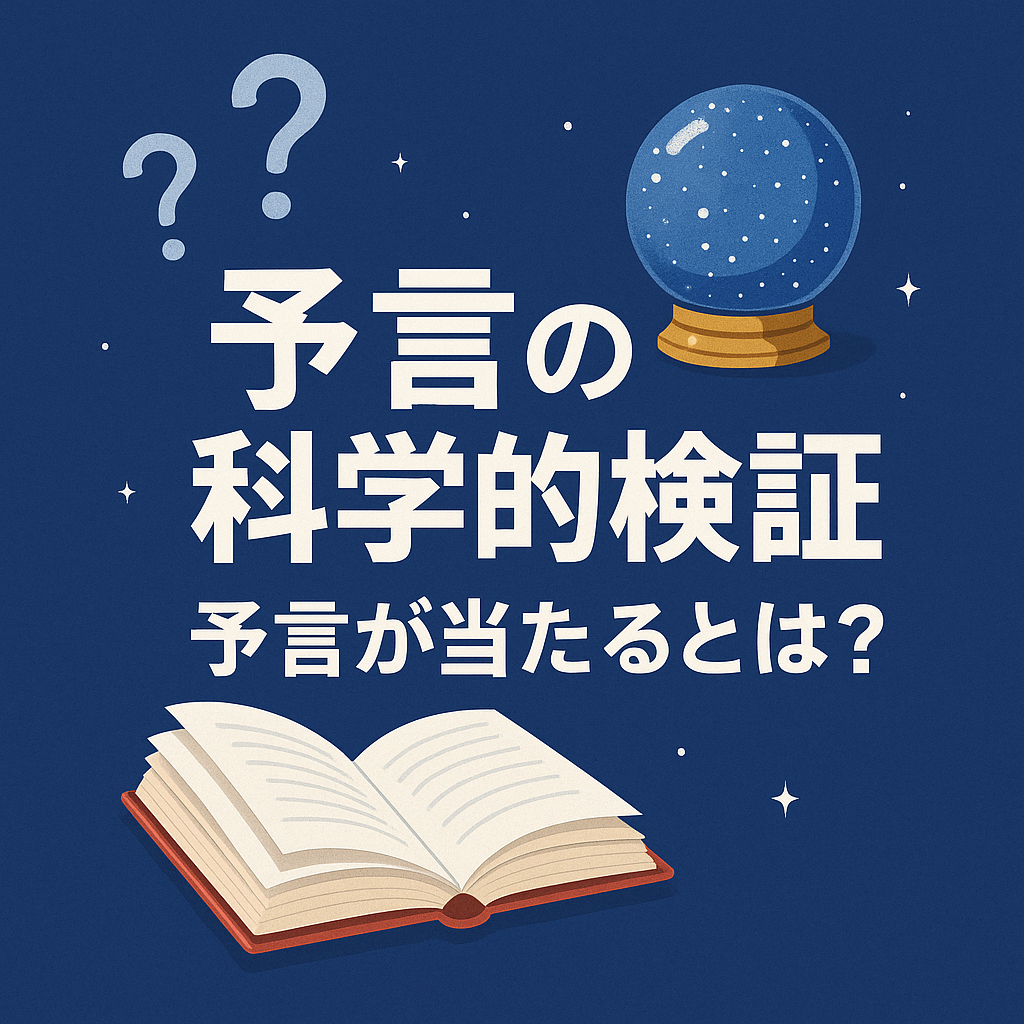
『准教授 高槻彰良(たかつきあきら)の推察』で感じた「予言」との向き合い方
オーディブルで聴いている『高槻彰良の推察』ですが、高槻先生のイケメンぶりと深町尚哉君の成長を聴き続け、11巻のうち9巻まで聴いています。その中に登場した「予言」に関する考察が、自分にとって非常に興味深いものでした。特に「人は理由のない出来事を意味づけたがる存在だ」という点に強く共感しました。
予言はなぜ当たったように感じるのか?
たとえば「2025年に日本で大きな地震がある」という予言があったとします。地震大国である日本では、大小の地震が毎年起きています。そのため、「ほら当たった」と感じやすいのだそうです。
このような現象を心理学では「確証バイアス(Confirmation Bias)」と呼びます。つまり、自分にとって都合のいい情報ばかりを集めて、あたかも予言が的中したかのように思い込む傾向のことです。
科学的に予言は可能か?
現在の科学では、気象や地殻変動などの分野において「ある程度の予測」は可能です。しかし、数年先の未来をピンポイントで当てるような「予言」は、科学的に証明されていないそうです。
例:
- 地震予知は現在でも確率的にしか行えず、「○年○月○日」と断定するのは不可能です(参考:地震調査研究推進本部)。
- 太陽活動や惑星の配置から未来を読む占星術も、科学的根拠が不十分とされています(参考:American Astronomical Society)。
なぜ人は予言に惹かれるのか?
最近は、政治的にも経済的にも不安定な状況が続いています。そのように不安や不確実性が高まると、人は「何かにすがりたくなる」傾向が強くなるようです。予言は、未来の不安を“言葉”で与えてくれる存在であり、ある種のスケープゴート的に機能するように思います。
さらに、予言には「物語性」があるため、印象に残りやすく、人の記憶にも残りやすいのです。
ノストラダムスや『私が見た未来』はなぜ話題になるのか
ノストラダムスの予言や、たつき諒さんの『私が見た未来』のような作品は、内容の曖昧さや象徴性によって、どのような出来事にも「結びつけやすい」のが特徴とも言えます。
これは「バーナム効果」と言われるものと関係しているそうです。
→ 誰にでも当てはまりそうなことを言われると、自分だけに当てはまると感じる心理現象です。占いなどでもこのバーナム効果を利用する場合があるそうです。
予言が“当たる”とはどういうことか?
科学的にいえば、予言が当たったというには次の条件が必要だそうです。
- 予言内容が明確で、曖昧でないこと(日時・場所・現象の特定)
- 事前に記録・公開されていたこと(あとづけでない)
- 統計的に偶然とは言い難い再現性があること
しかし実際には、多くの予言は「解釈の余地」を残して書かれており、後から当てはめることができるようになっています。どちらかというと予言の方に自分の解釈を寄せてくるような感覚になると思いますが、これにより「当たった」と錯覚してしまうらしいのです。
予言よりも「今、何を選ぶか」
コーチング的に言えば、予言に一喜一憂するよりも、自分自身が「どんな選択をし、どう行動するか」が未来をつくるのではないでしょうか。
未来は決まっているものではなく、自分の一つひとつの選択の積み重ねで形づくられていると考えています。
あなたの未来をより良いものに変えるとすれば今から何をしますか?

今日も佳き日に
コーチミツル
#予言の正体 #確証バイアス #バーナム効果 #ノストラダムス #私が見た未来 #高槻彰良の推察 #科学と心理 #コーチミツルブログ