
10年以上前ですが、早朝にランニングをするのが日課になっていたことがありました。
まだ静まりかえった町の中、清々しい空気を胸いっぱいに吸いながら、誰かとすれ違うたびに「おはようございます」と声をかけるのが、なんとも気持ちの良い習慣だったのです。
そんなある朝のこと。
いつものようにすれ違う男性に挨拶をすると──
「はい」
という一言だけが、ポツンと返ってきました。
返してくれただけありがたい。頭ではそう思いながらも、心のどこかがモヤモヤとしました。
それからというもの、似たような場面がいくつか重なり、自分は内心で、そういう返答をする方々を“ハイおじさん”、略してハイおじと呼ぶようになってしまいました。(もちろん、本人に言ったりはしませんよ。あくまで心の中だけの呼び名です。)
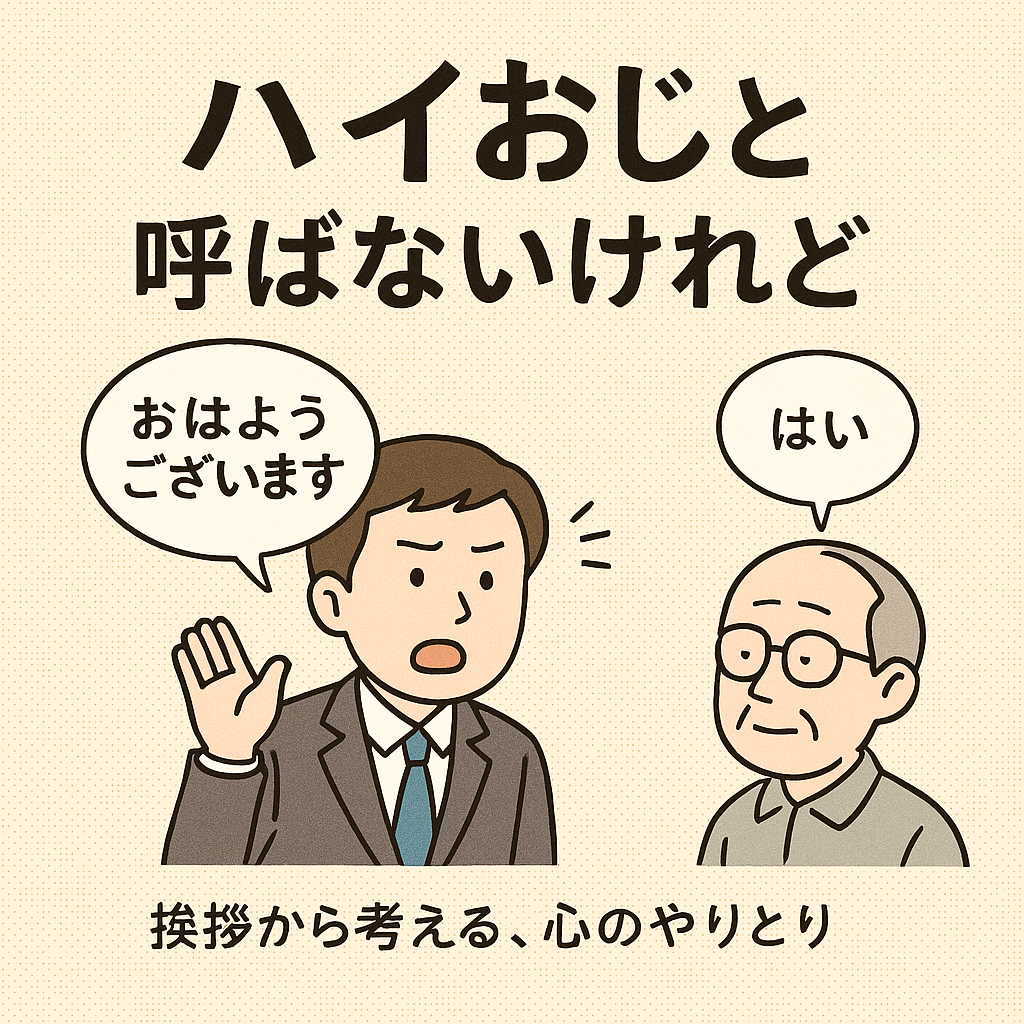
挨拶(あいさつ)の、本当の意味
挨拶(あいさつ)の語源をご存じでしょうか?
「挨(お)す」は“近づく”という意味、「拶(せま)る」は“踏み込む”という意味があるそうです。
つまり、挨拶とは**「心を開いて相手に近づく行為」**。
「おはようございます」という言葉には、
「あなたの存在を認めていますよ」「今日もよろしくね」という、目に見えないあたたかな気持ちが込められているのです。
そのやりとりの中で、「はい」とだけ返されると、
まるで扉をノックしたのに、ドア越しに一言だけぼそっと返されたような、そんな寂しさを感じるのかもしれません。
なぜ“ハイおじ”は「はい」と返すのか?
これはあくまで自分の推測ですが──
長年、職場などで“挨拶される側”の立場で過ごしてきた方々ではないかと感じています。
毎朝、部下から「おはようございます!」と声をかけられる中で、
「はい」「うん」とだけ返すことが習慣になっていった。
挨拶が、心のやりとりではなく、反応の儀式のようになってしまったのかもしれません。
慣れというのは怖いもので、ふとしたところで人柄や印象に影響してしまうことがあります。
本人に悪気はまったくなくても、無意識のクセとして染みついてしまっているのだとしたら……
なんだか、ちょっともったいない気もしますね。

なぜ男性に多い? “ハイおじ”という文化
観察していて感じるのは、こうした反応は圧倒的に中高年の男性に多いということです。
女性ではあまり見かけたことがありません。
これは日本の社会構造、特に昭和や平成の「男社会」の影響もあるのかもしれません。
感情をあまり表に出さず、上下関係を大切にし、無駄な言葉は控える──
そういった価値観の中で育ってきた方々にとって、「挨拶」は言葉よりも形式に重きを置かれていたのかもしれません。
海外では挨拶、どうしている?
海外に目を向けてみると、挨拶はもっとフレンドリーな関わりの始まりとして使われています。
アメリカでは「Hi!」「How are you?」に、「Hi! I’m good, thank you.」と笑顔で返すのが日常ですし、
フランスでも「Bonjour!」には「Bonjour!」ときちんと返すのが礼儀です。
挨拶というのは、その国の文化や人間関係の在り方を映す鏡のようなもの。
言葉そのものより、気持ちのやりとりが大切にされているかどうかが大きな違いかもしれません。
子どもと挨拶、そして地域のつながり
最近では、「知らない人には挨拶をしないように」と学校で指導されることがあると聞きます。
防犯上の配慮だと思えば理解できる一方で、少し寂しさも感じます。
本来、地域での挨拶は、知らない人を“知っている人”に変える第一歩。
大人同士が顔を合わせ、「おはようございます」と自然に挨拶を交わす。
そんな風景を、子どもたちが日常的に見ていれば、安心して声をかけられる環境も育まれるのではないでしょうか。
子どもを守るのは、大人の注意だけでなく、地域のつながりなのだと、自分は思っています。
そして自分は、“ハイスペおじ”を目指したい
挨拶は、小さな光のようなものです。
ほんの一言でも、心を込めて交わされれば、その日一日をやさしく照らしてくれることがあります。
だから自分は、これからも「おはようございます」と声をかけ続けたいと思います。
たとえ返ってくるのが「はい」だけだったとしても、それで心が動くこともあるはずです。
でも……どうせ“ハイおじ”になるなら──
自分は、挨拶に心を込められる“ハイスペックおじさん”、略して ハイスペおじ を目指したいと思っています。
笑顔で人に声をかけられる。
場の空気をあたためられる。
そして、自分の言葉で周りの人にちょっとした元気を届けられる。
そんなおじさん、かっこよくないですか?
今日もあなたに、「おはようございます」。
それが届いて、あなたの心に小さな光が灯りますように
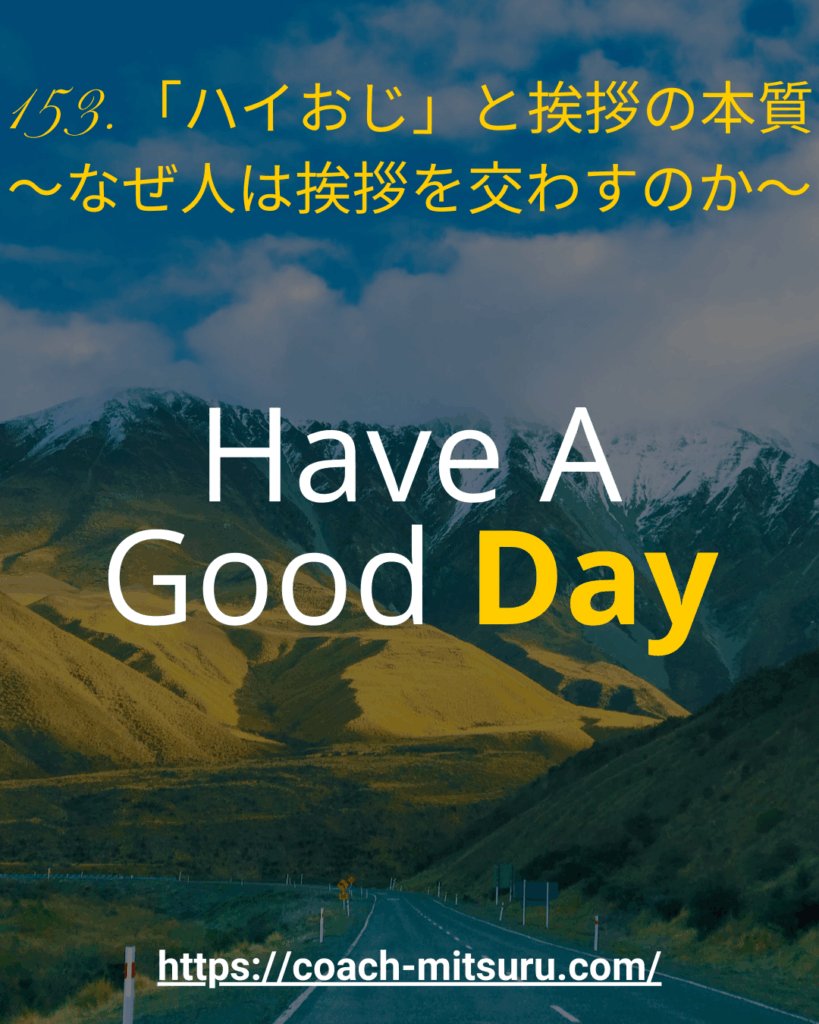
今日も佳き日に
コーチミツル








