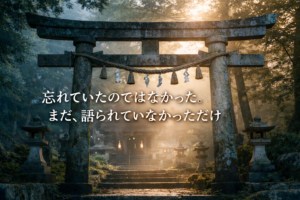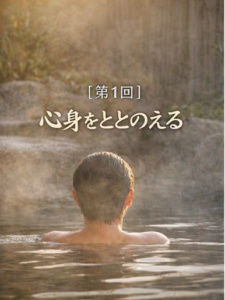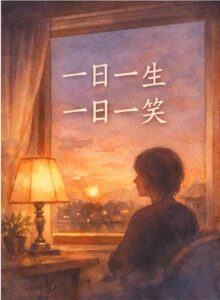TV番組 ウワサのお客さまを観られた方もあると思いますが、
本日はレジェンド寮母村野さんによる出張クッキング企画がありました。
今回は八王子学園八王子高等学校・吹奏楽部に出張クッキング
ということで全国大会2年連続金賞を目指す部員たちへ、れんこんオムハヤシライス、にんじんとりんごのはちみつサラダ、ねぎぽん酢スープなど130人の部員の食事を部員のお母さまと一緒に調理されました。
美味しそうにおかわりする部員の姿を観て微笑ましくなりましたが、これだけ多くのメンバーがどれだけ音楽演奏を生涯の趣味として続けるのかなあという想いが出てきました。
自分たちが学生の時もそうでしたが
中高6年間吹奏楽を真剣に取り組んでいても大学もそうですが社会人になっても続けている人は、感覚的に1割程度くらいかなあと感じています。
音楽は運動よりも長く続けることができそうですが、続けられない理由を自分なりに考えてみました。
- (1)楽器を買うか借りるかして用意しないといけないこと。
- (2)ある程度大きな音を出せる環境が必要なこと
(3)一緒に演奏できるできるメンバーがいないといけないこと -
などなどあると思います。
そこで、AIのChatGPT君にエビデンスを提供してもらいました。
(1) 全日本吹奏楽連盟のデータ
• 全日本吹奏楽連盟の加盟団体数を見ると、中学・高校の吹奏楽部は約7,000校に対し、一般団体(社会人バンドなど)は約400団体程度とされています。 これは、学校で吹奏楽を経験した人のうち、社会人バンドなどで活動を続ける人はごく一部であることを示唆しています。
つまりは、楽団が少ないということですよね。現役からすぐに入るならまだしも、ブランクがあれば演奏の自信も無くなるし、自分の演奏する楽器メンバーがある程度揃っていると楽団に入りにくいようにも思います。
(2) アンケート調査の例
吹奏楽経験者向けのアンケート調査では、以下のような結果が示されています。
• 「社会人になっても吹奏楽を続けているか?」という質問に対し、**約10~20%程度の人が「続けている」**と回答する傾向がある。
• 一方で、「また機会があればやりたい」と考えている人も30~40%程度いるということで仕事や家庭の状況により、一時的に離れても再開したいと考える人は多いと読み取れます。
続けたい気持ちがあってもなかなかできないのが実情で
その受け皿があると良いのではないでしょうか。それも上手い下手をとやかく言わずみんなで楽しむことが目的のようなバンドであったり、デュオやトリオ、カルテット等少人数でも演奏できるようなメンバーで活動できるとみんなが続けてくれるのではないかと感じました。

30年間ブランクがあった自分に声をかけてくれたメンバー、所属するビッグバンドのメンバー、セッションをしてくださる師匠や諸先輩方に演奏活動を続けさせてもらっていることに感謝しております。
そして、青春の大切な時期、一所懸命に音を紡いでいる若い人たちを観て”やめるのもったいない”そんなことを思った次第です。

今日も佳き日に
コーチミツル