「過保護」という言葉を耳にすることがありますが、ではその反対は何でしょうか?
多くの方が思い浮かべるのは「放任」や「無関心」かもしれません。
けれど、子どもの成長を願う私たち親にとって、ただ見放すことが正しいとは思えませんよね。
自分はコーチングを学ぶ中で、**過保護の本当の反対は「自律支援」**なのではないかと感じるようになりました。
今回は、「子どもが自分で考える力を育てるには?」という視点から、過保護との向き合い方について考えてみたいと思います。
雨の日に見える「過保護」の一面
最近では、雨の日になると、子どもを車で学校まで送り届ける光景をよく見かけます。
親御さんの「風邪をひかせたくない」「事故が心配」というお気持ちはとてもよく分かりますし、現代の社会事情を考えれば無理もありません。
ただ、自分自身の子ども時代を思い返すと、少し違う風景がありました。
雨の日はカッパを着て自転車で登校し、
雪が積もれば、朝早くから家を出て1時間かけて中学校へ歩いて通っていました。
送り迎えはなく、自分で状況を判断して動いていたように思います。
「どの道を通れば滑りにくいか」「どうすれば濡れずに済むか」
軒下を渡り歩きながら(笑)そうした判断を、誰に教えられるでもなく身につけていたのです。
子どもが“自分で考える力”を育てるには?
コーチングでは、「なぜできなかったのか?」と原因を追及するのではなく、
「どうすればうまくいくと思う?」と未来志向の問いかけを大切にします。
たとえば、朝の準備がうまく進まない子どもに対しては、
- 「今日は何から始めるといいかな?」
- 「前にスムーズにできた日があったよね。その時は何をしたかな?」
といった質問をすることで、子ども自身の中にある“できた経験”や“工夫”を引き出すことができます。
これは、失敗を責めるのではなく、子どもが自分で考え、選び、行動する力を信じて支える姿勢です。
過保護の反対は「自律支援」
あらためて言葉にするなら、
私が考える過保護の反対は、**「自律支援(Autonomy Support)」**です。
それは、子どもを信じて任せること。
困ったときに助けられるよう距離をとりながら、問いを投げかけ、
子どもが自分の頭で考える機会を大切にする関わり方です。
親が全部やってしまえば、子どもは“失敗しない”かもしれません。
でもその分、“考える機会”も“学ぶチャンス”も減ってしまいます。
遊びの中にも「考える力」のヒントがある
今の子どもたちの遊びは、とても便利で快適です。
ゲームのスイッチを押せばすぐに始まり、説明書どおりに動かせば楽しく遊べます。
けれど、私たちが子どものころは、遊びそのものを工夫してつくっていた気がします。
空き地に線を引いてベースを作り、紙を丸めてテープでぐるぐる巻きにしてボールを作り、木の棒をバット代わりにして野球をしたり。
何もない中から遊びを生み出す力が自然と育っていました。
遊びの中にも、「考える」「工夫する」「仲間と話し合う」力がたくさん詰まっているのです。
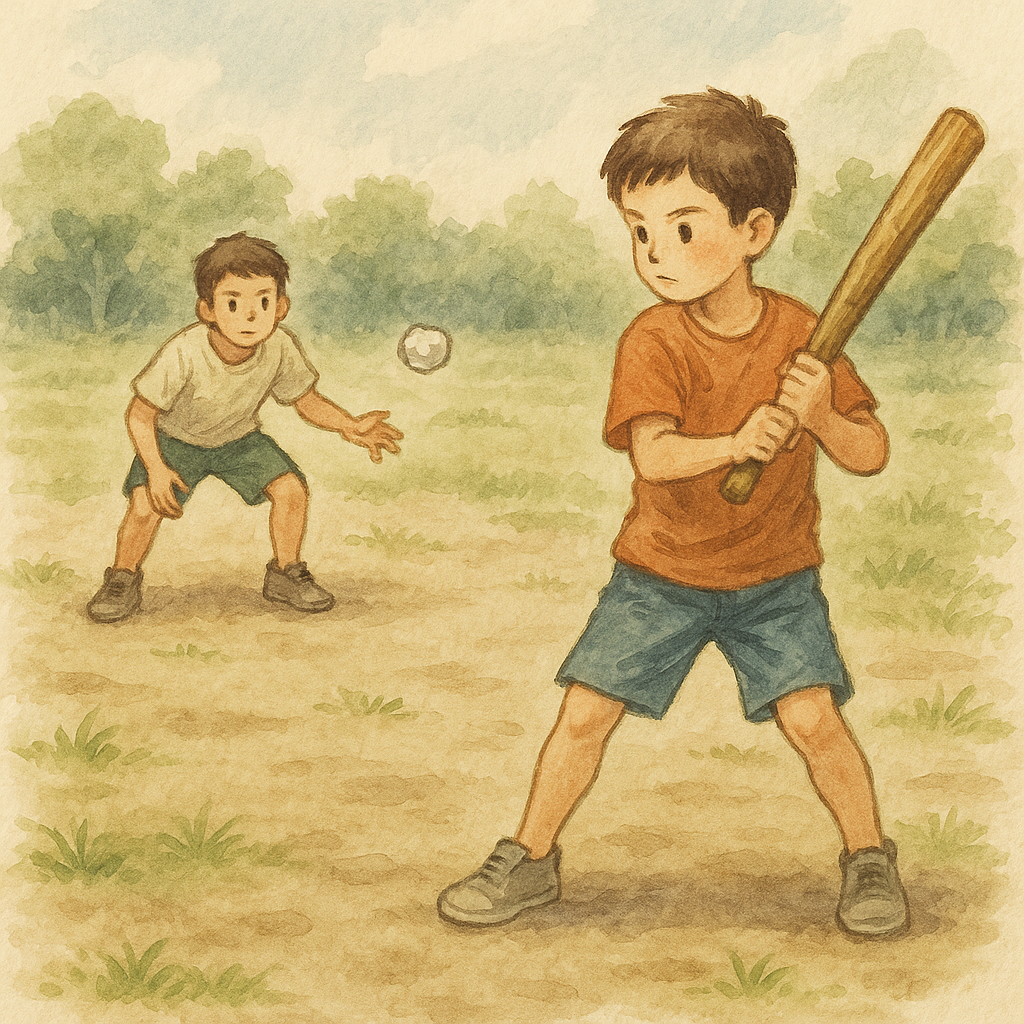
家庭でできる「自律支援」の工夫3つ
子どもに“考える力”を育てるために、家庭でできることを3つご紹介します。
① 先回りしすぎない
忘れ物をしても、次から気をつけるきっかけになります。
すぐに助けるのではなく、「自分で気づく」体験を大切に。
② 質問で関わる
命令や指示ではなく、「どうすればいいと思う?」と考える余地を残した問いかけを。
③ 退屈な時間をつくる
あえて何も予定のない時間をつくることで、子どもが「何をしたいか」を自分で考えるようになります。
信じて、任せて、見守る子育てへ
親として、「困らせたくない」「失敗させたくない」という気持ちは自然なことです。
でも、子どもの“考える力”を育てるには、ちょっとした勇気と信頼が必要です。
子どもは、失敗を通して成長します。
「どうしたらいいか」を考える経験こそが、これからの人生を生きていく土台になります。
私たち大人にできるのは、
その成長のチャンスを奪わないこと、そしてそっと支えることかもしれません。
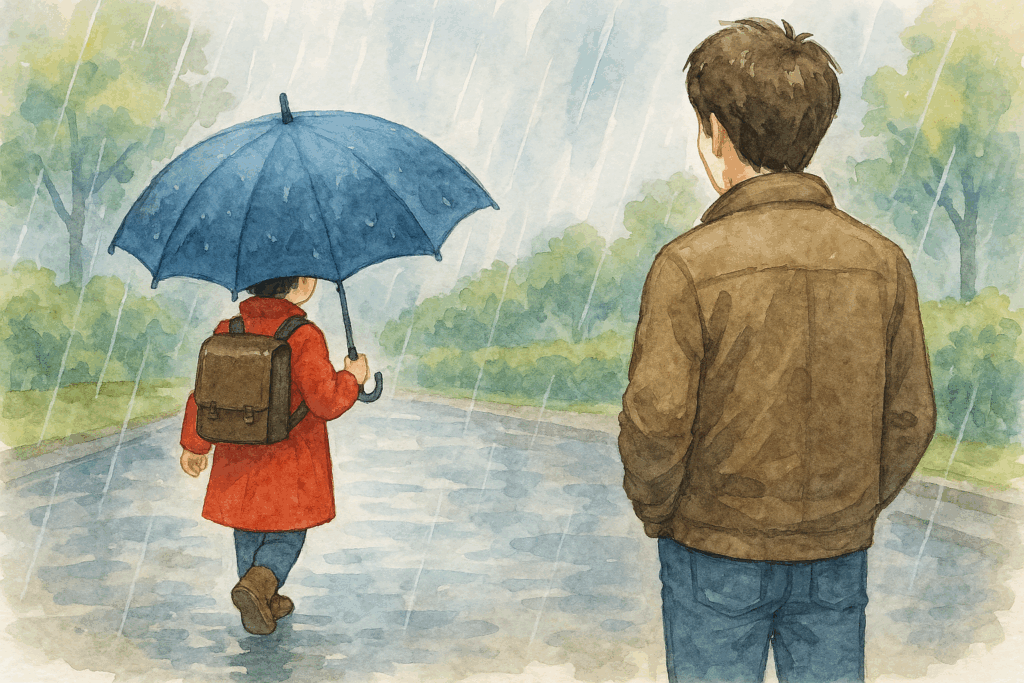
今日も佳き日に
コーチミツル
#子育て #過保護 #自律支援 #考える力を育てる #コーチング #問いかけ #親の関わり方 #子どもの自発性 #教育コーチング #子どもを信じる








