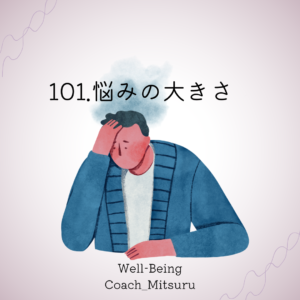おかげさまで101回目のブログ更新をさせていただくことができました。
この場をお借りして皆様に感謝申し上げます。
さて、今日のお題の”悩みの大きさ”と言うテーマですが、
人それぞれ大小様々な悩みを持っていると思います。その大小という悩みですが、これもきちんと数値で表せるものでなく、全くもって主観的なものではないでしょうか?同じことが起きたとしても人によってそれが大きな悩みになったり、たいしたことではなかったりするように思います。
自分は子供の頃、極度の心配性でした。
何をするにしても心配になってきます。学校の宿題や持っていくもの、遠足の時も車酔いがひどく、気になって眠れないこともありました。また、大きなイベントである、運動会や演奏会などがあると、当日か翌日に高熱が出て学校を休むこともしばしばでした。
時々、お袋に、「○○がどうなるかわからないので心配だ。」等と相談もしていましたが、「あんた、そんな小さなことで悩んでいるの?大丈夫、何とかなるから。」という言葉で背中をたたいてもらっていました。
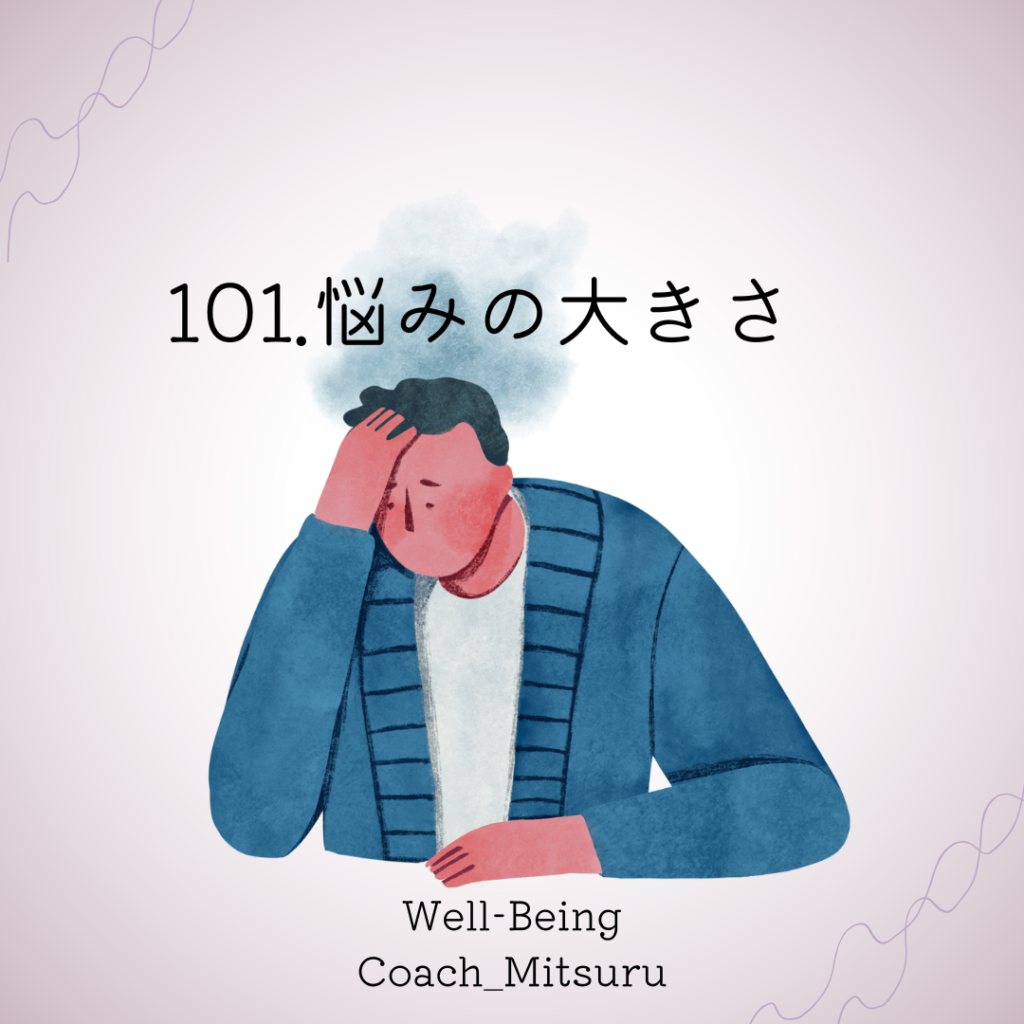
その悩みの大きさについてですが、
確かに、当時の私にとって大きな悩みは、大人にとっては小さな悩みだったと、もちろん、当時の自分の悩みを想い出せないくらいですから、今の自分にとっても小さな悩みなのかもしれませんが、小さな自分にとっての悩みは本当に大きかったように思います。
そんなことを考えて思いついたのは、この悩みの大きさとは、人間それぞれの経験値の大きさに反比例するのではないかと感じています。
当たり前と言えば当たり前ですが、例えば、初めて子供を授かり子育てを始めたパパとママがいたとします。最初のうちは赤ちゃんが泣いている理由がわからず、おむつを見たり、ミルクをあげたり、抱っこしてみたり、それでも結局わからず、悩み疲れてしまうことだってあります。ですが、それを繰り返しているうちに経験値が上がり少しずつ赤ちゃんのことが分かってきて、次第に顔の表情や声のトーンだけで、状況が分かるようになる。
そして、2人目以降の赤ちゃんを育てるようになると、経験値が上がり悩みも少なくなり比較的楽に子育てができるようになる。もちろん、子供が大きくなってくれば、それはそれで、レベルアップした悩みも出てくるかもしれませんが・・・。
他にも、初めての仕事をしたときと1年やってみて、次の年も同じ仕事だとしたら悩みの大きさも変わってくるでしょう。
このように経験値がその悩みの大きさを決めているということになると、
最初の子供の頃の悩みというのは、まだ、この世に生まれて数年の子供の悩みというのは、大人が一方的に小さな悩みと言い切れるものではないと考えています。経験値が少ない子供が、しっかりと経験して自分のものとして、悩みを克服し、自信をつけ、ずっと学び続ける子供になるために、大人は協力する必要があると思います。
では、子供の悩みに対して、どうすればよいでしょうか?
私はコーチングを学んでいますので、その立場からお話しさせていただくと、このようなアプローチになるかと思います。
- ①子供の悩みを否定しないで積極的に傾聴する。
子供にとっての悩みの大きさについては、本人の気持ちを大切にして、大人が勝手に悩みの大小を判断せずに、どん
な悩みなのか、相づちを入れ、うなずきながらしっかり聴く。そして分からないことは訊いてみる。
②その悩みを子供の立場として共感する。
子供の悩みとしてではなく、自分がその立場だったらどう感じるかを、子供の頃に戻って理解し共感する。
③その悩みにどう向き合えばよいか質問する
悩みについてお互い理解が深まったら、悩みを克服できるために子供がどう向き合うのか、何ができるのかを訊く。
④自分がフォローできることを訊く
子供だけでは解決できないこともあるので、親としてフォローできることを訊く
つまりは、子供の経験値をどんどん積み重ねていけるよう、否定せずフォローしていくというスタンスが良いのではないかと思います。
もちろん、その悩みを、克服することができれば一番良いのですが、
大人にとっても大きな悩みで、場合によっては克服と言いますか超えることができないこともあると思います。そんな時は、逃げることも選択肢としてあってもよいかもしれませんね。なぜなら、猛獣が相手であれば、闘うより逃げる方が、安全であり得策ですからね。
悩みは経験値に反比例する
今日も佳き日に
コーチミツル