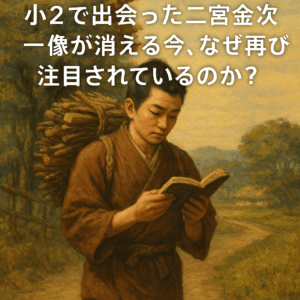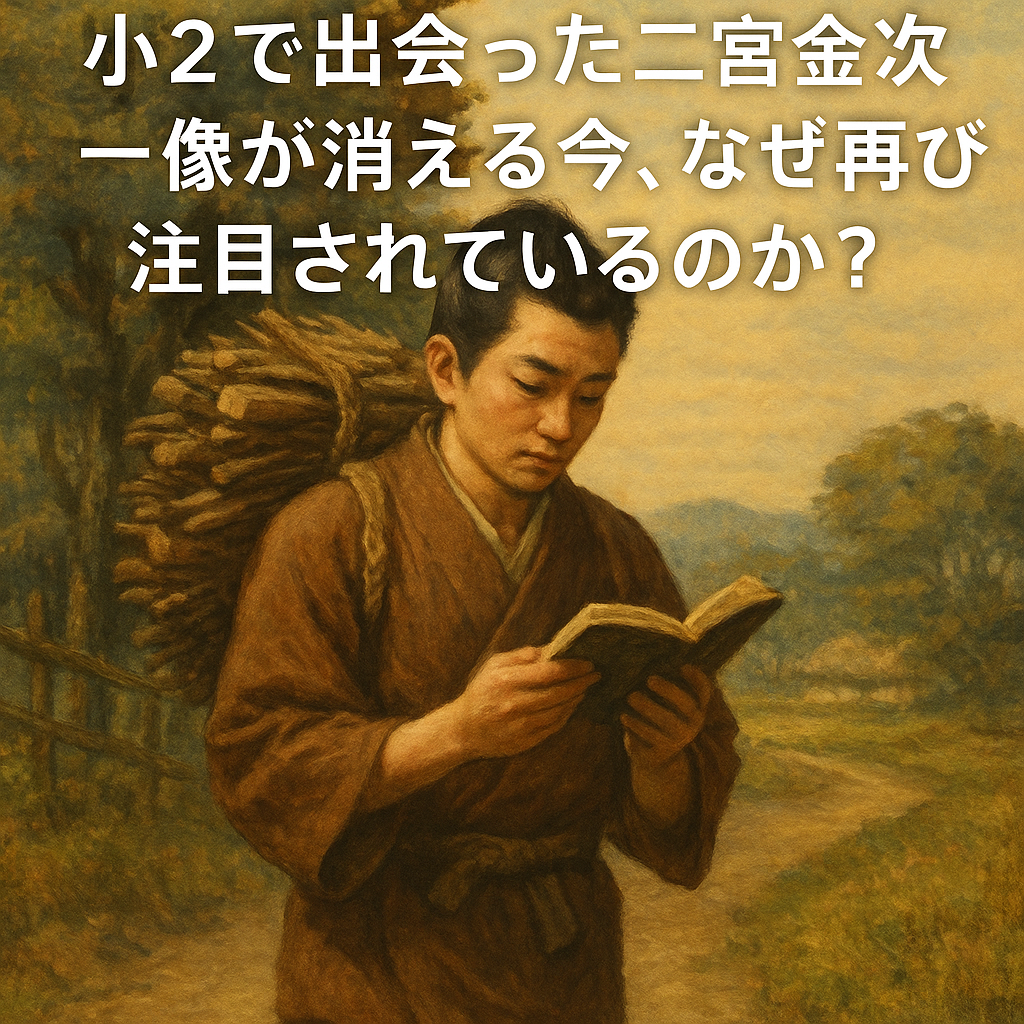
小学校2年生で出会った二宮金次郎の記憶
小学校2年生のころ、二宮金次郎の伝記を読み、読書感想文を書いたことがあります。
当時の自分にとって「金次郎=勤勉で努力の人」というイメージはとても強く、薪を背負って歩きながら本を読む姿に、ここまで時間を惜しんで勉強しているのかという思いを抱いていました。
仕事をするようになってから、休日に実家の田んぼの代づくりをするときに、英会話の音源を聴きながら耕運機で耕していたことがありましたが、もしかしたら二宮金次郎を見習っていたのかもしれません。(笑)
また小学校の校庭には結構な確率で金次郎像があり、それは“学校の風景の一部”として当たり前の存在でした。
自分と同じような記憶を持つ方も多いのではないでしょうか。
いつの間にか姿を消し始めた金次郎像
ところが近年、「金次郎像が撤去されつつある」という話を耳にします。
理由として挙げられるのは、
・歩きながら本を読む姿が「歩きスマホのように危険」と見られやすい
・“勤勉の押しつけ”という印象を与えてしまう場合がある
・教育現場で価値観が多様化し、象徴として扱いにくい
といった背景です。
かつて当たり前だった像が、気づけば校庭から少しずつ消えていく。
時代の変化を象徴しているように感じます。
そもそも「歩きながら読書」は本当だったのか?
この有名な姿ですが、実際に金次郎が“歩きながら本を読んでいた”という確実な記録は多くありません。
むしろ、
「忙しい農作業の合間を縫って学び続ける姿勢を象徴として描かれた」という説のほうが強いようです。
歩き読書の“正確さ”よりも、限られた時間でも学ぶ工夫をした少年の姿勢こそが本質だと考えられています。
勉強するための行灯の油を“自分でつくった”という象徴的な物語
金次郎にはもう一つ、とても有名なエピソードがあります。
■ 行灯の油すら買えない貧しさ
幼少期の金次郎の家は非常に貧しく、夜に勉強するための行灯の油を買う余裕がありませんでした。
■ そこで、自分で菜種を育てた
金次郎は耕作を許されていた小さな土地に菜種をまき、自分で世話をし、実った菜種を油にして、勉強の明かり代を自分でつくり出したと伝えられています。
■ 実話かどうかより「象徴性」が重要
研究者の中には「実話として確証は薄い」という見方もあります。
一方で、尊徳の姿勢を象徴する教育物語として語られてきたという側面もあります。
ただ、どちらにしても“学ぶための環境すら、自分の手でつくり出した”という精神は、尊徳の生き方そのものです。
歩き読書が象徴だったように、この油の物語も、尊徳の本質を示す大切なエピソードだと感じます。
像は減っている。でも尊徳は“再評価”されている
金次郎像は時代とともに数を減らしました。
しかしその裏側で、二宮尊徳の思想はむしろ注目度が高まっています。
作家・北康利さんの新著をはじめ、尊徳を“勤勉の象徴”としてではなく、荒れた村を再建した実務家・改革者として再評価する流れが生まれています。
歩き読書や油の物語の“事実性”よりも、彼が持ち続けた 「学び続ける姿勢」「自分から工夫する力」
こそが現代に響くのではないかと感じています。
“記号は消え、本質だけが残る”という現象
金次郎像という象徴は、時代の流れの中で姿を消しつつあります。
しかし、象徴は薄れても本質はむしろ強く残る。
それが、二宮尊徳という人物の面白さだと思います。
時代が変わっても、誠実さや学び続ける姿勢といった“普遍の価値”は変わらないからです。
最後の問い
あなたにとって、子どものころに見た金次郎像はどんな存在でしたか?
どんな記憶や印象が残っていますか?
次回予告(第2回/全4回)
次の記事では、
「尊徳は“努力の象徴”ではなく、村を立て直す仕組みをつくった人」
としての本質に迫っていきます。
今日も佳き日に
コーチミツル
二宮金次郎 #二宮尊徳 #報徳思想 #積小為大 #菜種油の物語 #学び続ける力 #勤勉の象徴 #歴史の再評価 #北康利 #チームビルディング #教育と価値観 #朝自活 #WellLog #コーチング視点