おかげさまで333回め、365日までの最後のゾロ目ですねー、閲覧回数爆発的に伸びたりして〜笑
行列のできる人気ラーメン店での出来事
先日、昼食に立ち寄った人気ラーメン店で、思いがけない体験をしました。
その店は平日でも行列ができ、スープがなくなり次第終了するほどの人気店です。
席に座ってラーメンを待っていると、店内のBGMがふと耳に引っかかりました。
「ん? この感じ、どこかで聴いたことがあるような…?」
初めて聴くはずなのに、知っている曲に似ている空気をまとっている。
その瞬間、思わず箸を止めて耳を傾けてしまいました。
正直に言えば、「Billy’s Bounce (ビリーズ・バウンス)に似てるな…もしかしてパクリ?」
とまで思ってしまうほどでした。
Shazamで調べると“本当に初めての曲”だった
気になって、スマホの音楽検索アプリ Shazam(シャザム) を開きました。
Shazamは、
・流れている音楽を数秒聴かせるだけで
・曲名とアーティストを教えてくれるアプリです。
数秒後、画面に表示された曲名は “El Sino(エル・シノ)”。
曲名を見ても記憶がなく、やっぱり初めて聴いた曲だったことがわかりました。
“似ているなあ”という感覚は誰にでも起きる
音楽を聴いていて、
「この曲、あの曲に似てる」
「どこかで聴いた気がする」
と感じることは誰にでもあります。
自分が耳が特別良いわけでもなく、ジャズ通だから気づいたわけでもありません。
ただ自然に、
「似てる気がする。なんでだろう?」
と気になり、深掘りしてみた──
たったそれだけです。
でも調べていくうちに、その“似ている感覚”にはきちんと理由があると分かりました。
似ている理由:音楽の“語り方”が近かった
El Sino と Billy’s Bounce を比べると、
実は曲そのものより 音の語法が近い のだと気づきました。
- メロディが“しゃべる”ように進む
- ブルースの匂いが強い
- 跳ねるスウィング
- コール&レスポンスの構造
つまり、
曲の骨格は違っても“話し方”が似ていたわけです。
だから耳が自然に
「知ってる感覚」
「似てる感じ」
をキャッチしたのだと思います。
年代を辿ると“似て当然”だった
さらに年代を調べると、
- Billy’s Bounce:1945年
- El Sino:1947年
ほぼ同じ時代の曲でした。
ビバップ期のブルース文化のなかで生まれた曲どうしであれば、似た空気を感じるのは当然のこと。
「だから似て聞こえたのか」と納得がいきました。
El Sino Clubという実在のクラブにつながった
“El Sino”を調べていくと、
デトロイトの El Sino Club という実在するジャズクラブに辿り着きました。
1940〜50年代のジャズの中心地、ハスティングス・ストリート。
パーカーやマイルスも出入りしたといわれる場所。
その空気感が曲名にも残っていると思うと、
突然ラーメン屋で遭遇したあの音が、歴史の奥へとつながっていくようでした。
違和感は、小さな深掘りの入口になる
今回の体験で気づいたことがあります。
ただの「似てるなあ」という違和感が、深掘りの入口になる
ということです。
その違和感を少し追いかけただけで、
- 音楽の背景
- 時代の流れ
- ジャズ文化のつながり
が見えてくる。
ラーメン屋で箸を止めた数秒が、思いがけない“音楽の旅”の始まりになりました。
あなたはどんなときに“似てる”と感じますか?
今回の経験を通して、日常の中の小さな違和感には、思わぬ発見が隠れていると感じました。
あなたは最近、「あ、これ何かに似てる」と思ったことはありますか?
そしてその感覚の奥には、どんな理由が隠れているのでしょうか。
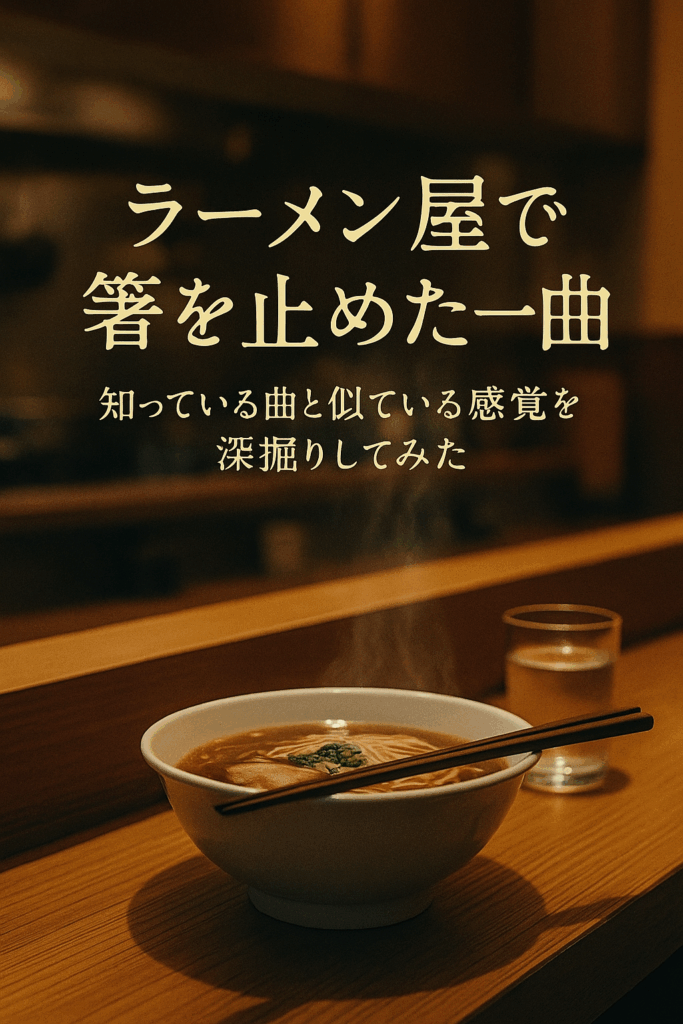
今日も佳き日に
コーチミツル
#ラーメン #ジャズ #ビバップ #ブルースジャズ #ElSino
#BillysBounce #Shazam #音楽の気づき #日常の発見
#コーチング #松江ランチ #行列のできる店








